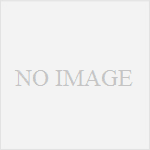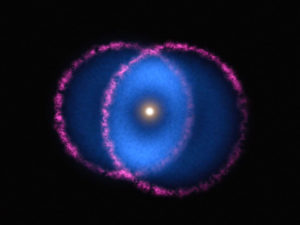
幽体離脱という言葉はお聞きになったことがあると思います。体から魂が抜け出して、自分の意志とは別に体外をさまようことを言います。よく、ホラー映画やアニメの題材になりますね。
私の子どもの頃、ウルトラQという番組があって、そこで女の子の魂が女の子の身体から抜け出して、列車の通る線路まで女の子の身体を誘い出すというストーリーがあり、それはとても怖い思いをしたことを覚えています。
ウカウカと寝てられないな、と思いました。
幽体離脱とヘミシンク
幽体離脱を学術的に言うと「体外離脱」といいます。(全然同じじゃないか、って感じですが。)
ヘミシンクって聞いたことがありますか。グーグルとかで検索すると怪し気なサイトがたくさん出てきます。
ヘミシンクは、Hemisphere-Synchronizationの略で、そのまま日本語訳すると脳半球の同調って意味です。脳半球は左脳と右脳があるのはご存知かと思いますが、その左脳と右脳の脳波が同調して脳全体の活動が活発化することを言います。
ヘミシンクの原理を発見したモンロー研究所というところは、この同調を利用すると体外離脱が可能だと言っています。この手の話にはよくある話ですが、どうして体外離脱するかは科学的な説明がありません。
そのヘミシンク状態を作るには、左右の耳からわずかに異なる(5ヘルツくらい)音を聴く、という単純な方法が用いられます。たったこれだけのことで体外離脱への道が開けます。
私も興味があったので、フリーソフトを使って、自分で可聴音で5ヘルツ違う音を作って、左右の耳から聴いてみました。
モンロー研究所からは高価なヘミシンクキットが出ているのですが、やっていることはこれと同じことなので、購入しなくても体験はできます。
ヘミシンクとEMDR
確かにヘミシンクで使われているような倍音のうなりが聞こえるのですが、それを聞いていると気分が悪くなりました。この気分の悪さは前にも体験したなぁ、と思っていると、EMDRをやってもらったときの体験と似ていました。
EMDRとはEye Movement Desensitization and Reprocessing の略で「眼球運動による脱感作と再処理」という、なんだかややこしい日本語に訳されています。
これは何をするのかというと、トラウマ記憶が出てきたときに、目の前で指を左右に動かして、それを見つめつづけることで、PTSDなどのトラウマによる症状を緩和させるテクニックです。病院などでも使っているところがあります。
EMDRがなぜトラウマ解消によいのかの科学的な説明はなされていませんが、
経験上良いようです。眼球運動が脳の記憶の貯蔵庫である海馬に働いて、心的外傷となる記憶を緩和させるという仮説があります。
それで、この目を左右に動かす運動をしたときの気持ち悪さと、ヘミシンクを聴いたときの気持ち悪さが似ていたのでした。
(と、すると、ヘミシンクはEMDRと同じトラウマ解除効果があるのか!?)
この気持ち悪さは、たぶん脳のどこかが活性化されすぎたのかもしれません。脳波を見ていたわけではないので単なるあてずっぽです。科学的に説明のつかないことは日常でも多々あり、高速鉄道や病院のMRIで使われる超伝導という現象でも、まだまだ量子論で説明できないところがあります。科学的に説明できないが、それが使えるので使っているという技術は、そんなに珍しいことではないんですよね。
もし両方に同じような脳波状態が現われていたら、ヘミシンクで体外離脱するなら、EMDRでもその可能性があるということですね?こういう訳の分からないことを話しているとEMDRの先生からお叱りを受けそうなので、このへんで止めておきます。
体外離脱までいかなくても、ある種の軽い解離状態にはなるのかもしれません。
解離性障害
解離とは、感情と体験が分離している状態をいいます。感情と体験の間に分断があるとき、分断されてしまった感情を体験に呼び戻す、つまり感情と体験を一致させるという辛い作業によってトラウマは治癒していきます。
これは解離とは逆のこと(覚醒)をやっているわけです。EMDRによって擬似的に作り出される解離状態は、解離というよりその一歩手前、非常にクールに物事を見るという状態です。ただ、治療者によってこのコントロールがうまくいかないと、クライエントさんは解離の渦の中に引き戻され、セラピーを受けて症状が悪化したという治療トラウマを作ることになってしまいます。
EMDRは暴露による行動療法なので、再体験を強制的にさせます。ここがこの技法のもっている難しいところでもあり、使える人が限られるという限界もあるのでしょう。
体外離脱と臨死体験
さて、体外離脱をするとどうなると思いますか?
なんか素敵なことが起きる、素晴らしい才能が芽生える、そんなふうに宣伝しているのが、ヘミシンクを発見したモンロー研究所です。
でも、私は、体験的に、そうは思いません。体外離脱は誰でもできるテクニックですから。
瞑想のテクニックの中にも、あるイメージに導かれながら過呼吸を続けると体外離脱をする、そういう瞑想があります。これを応用した心理療法にパワーブリージングというテクニックがあります。トランスパーソナル心理療法で行われる一つです。
瞑想で変性意識状態になり、そこに過呼吸が加わることで、エネルギーが爆発して、それとともに魂が身体から抜けるような感じです。
(この表現は全然科学的じゃないですが、体験的にはこんな感じです。)
私は魂が身体から抜けるとき、臆病だから、抜けるのをためらっていました。かなり時間がかかりました。おっかなびっくりで、えいやぁ、と、なんとかして、頭から抜けてみました。
そしてしばらく身体の上空5メートルくらいを旋回していましたが、やがて100メートルくらいまで上昇し、周りの景色を楽しんでいました。
その間、身体は魂が抜けたままです。
高みの見物を楽しんで身体に帰ってみると、なんと身体が冷えていました!それ以来、数週間、ひどい風邪にかかってしまいました。身体から魂を抜かした罰を食らった感じです。それ以来、私は体外離脱をすることを止めました。
そこで得た教訓。
「体外離脱をすると風邪をひく」
これについてある人から言われたのは、私の場合、身体に帰ってみると身体が冷えていたということは、それは体外離脱体験ではなくて臨死体験だった、というのです。非常に危なかった、そうです。
普通、夜寝てしまうと意識を失い、意識は身体を抜けて「あの世」へ行っているが、普段の睡眠中は意識と身体はヘソの緒でつながっているそうです。
寝てしまうと、みんなの意識が天上界へ行くので、ヘソの緒がそこいらじゅうにあるわけで、からまって元へ戻れなくなってしまわないか心配ですが(笑)。
ヘソの緒でつながっているので、身体へ帰ってきたときも体温は維持されているそうです。
ただ、臨死体験は、三途の河へ行くだけなので、つまり帰ってくる予定がないので、ヘソの緒は切れるそうです。だからもし身体へ戻ったとしても、それは冷たい身体に戻ることになるそうです。
そんなわけで、私の場合、体外離脱したというより臨死体験だったということです。なるほど、それで冷たかったのか。
でも戻れてよかったと思います。まだやることがあります。(煩悩のカタマリの私です。)その瞑想を誘導していたのが、真言密教のお坊さんだったから良かったのかな。臨死体験だったら、もっと気をつけて、周りの風景を見ればよかったと思うのは後の祭りってやつですね。
ここまでが体外離脱のお話ですが、ここからが、心理領域の話です。
解離性障害に話を戻します
「体外離脱をすると風邪をひく」という教訓は、体外離脱を茶化しているわけではなく、体外離脱などの解離様の症状は、どこかで身体症状と密接に関係しているということです。深夜、鏡をのぞくと知らない人が鏡に映っているという体験をされた人もいるかとは思いますが、その解離状態のときも、身体は何かしらの信号をあなたに送ってきているはずです。
体外離脱とは、臨床心理でいうと、「その他の解離性障害」のなかの、離隔というジャンルに入る症状です。
解離性障害とは、アメリカの、症状と診断によるマニュアルDSM-IV-TRによると次の症状が該当します。DSM-5から少し区分が変わっていますが、臨床上はほぼ同一とみていいでしょう。
- 解離性遁走
- 解離性健忘
- 解離性同一性障害
- 離人性障害
- その他の解離性障害
遁走とは、今の生活のことをすっかり忘れ、どこか遠いところへ行ってしまう。
そのことを自分も分かってなくて、気がつくと遠くで生活していた、
というやつです。作家のアガサ・クリスティーにその癖があったのは有名です。
健忘とは、そのものズバリで忘れること。過去のある時期をすっかり忘れることから、自分の過去の人生すべてを忘れる(自分の名前さえも!)ことです。
同一性障害とは、別名、多重人格です。自分とは違う人格が現われて、自分とは違う自分で数時間をふるまうことをいいます。違う人格が現われているときは、
自分はどこにも居ません。別の人間にスイッチが切り替わる状態です。
これらはとてもドラマチックな症状ですが、これらの症状を目に見えて訴える人はそんなに居ないようです。よく見かけるのは、離人性障害と、その他の解離性障害です。最近はこの2つが解離の病態のメインと言ってもいいでしょうか。
離人はその他の解離性障害と同列で話すことができるので、その他の解離性障害について考えてみることにします。
解離の2パターン
さて、この、その他の解離性障害、2つのパターンに分けることができます。
1つは離隔(りかく)といいます。
自分や身体が、外の世界と分離している感じがする意識変容状態です。ボーッとしている、夢をみているよう、自分の実感がない、膜を通して外を見ているようだ、自分の身体感覚がない、などの症状です。これらは、普通状態でも体験することなので、病気と健康の境目に位置している状態ともいえます。芸術家が作家活動をするときは、ほぼ、この離隔状態に居るといえます。
もう1つのパターンは区画化といいます。
普通気づくことができることを意識して気づくことができなくなり、そのため行動や考えをコントロールできなくなり、生活に支障をきたす状態です。健忘、多重人格、手足が動かない、目が見えない、マヒ、運動障害、幻覚などが含まれます。
離隔とは意識変容状態で、
区画化とはコントロール不能状態といえます。
創造的な解離、病的な解離
体外離脱は離隔に含まれます。感情マヒ、離人症状、疎隔症状、体外離脱、自己像幻視などが離隔にはあります。
離隔には良い離隔と病的な離隔があり、その見極めが臨床的には重要になってきます。
体外離脱で一番肝心なところは、
体外離脱は意識変容状態によって起きるもので、
意識変容には、良いものと悪いものがある、ということです。
そして、創造的な意識変容は良いものに入ります。
例えば芸術家が芸術を生み出している時間は、この創造的意識変容状態にあるといえます。
音楽家が作曲に没頭しているとき、画家が絵を一心不乱に描いているとき、何かに乗り移られたようになっています。
これは精神医学の言葉を借りれば「憑依」そのものです。自分がどこかに行っている状態「離人」そのものです。
これらを病的と言う人は誰も居ません。芸術が生まれ出ている、創造的な瞬間は、まさに病的なものと紙一重なんですね。
これは何も芸術にかぎらず、宗教的な体験、大きな自然の中に身をゆだねているとき、夢を見ているとき、昔の思い出を思い出しているときなど、日常のささいな出来事の中にも、同様の創造的なものが潜んでいます。
文学作品や詩、童話、絵本の中にも潜んでいます。
体外離脱、幻聴、幻覚、憑依なんて話をすると、病的な部分のみが強調されて、
それが一人歩きすることが多いですが、それらの体験は、決して病的なものだけとは言えないのです。
特にこれらの症状から統合失調症を即断するような過ちは避けたいものです。
(こういうケースが結構多いですが。)
それらはあなた個人の身体の中の、創造的な領域とつながっているのです。どの人でもそうです。どこからどこまでが創造で、どこからどこまでが病的であるか、という問題は、答えるのが難しい問題です。
ただひとつ、困っているなら病的と言ってもいいだろう、その程度です。そして困っているなら何らかの治療が必要でしょう。
もしそれが困っていなければそれはりっぱな芸術の一つとして成長する可能性
もあるわけです。
このように体外離脱を含んだ解離という症状ですが、創造的な部分と密接に関係があるのです。