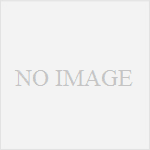意志や欲動という人間の基本的衝動を考えた場合、それらの衝動には、食欲などの身体的なものと、名誉欲などの精神的なものがあります。
食べられないという食欲の喪失は次のような可能性があります(Sims, 1988)。
1.おなかがすいたとか食べたいという欲求が欠落している。
2.空腹感はあるが、食べたいという動機が欠落している。
3.空腹感も食べたいという動機もあるが、食べようとする意志の異常がある。
4.空腹感があっても被毒妄想(毒をもられているのじゃないかと考える)によって食べたいという気持ちを抑制する。
実際にはこれらを区別することは困難で、食事をとらない病態は、
軽い意識混濁、うつ病、統合失調症、躁病、不安障害、摂食障害、重篤な身体疾患などで見られるものです。
食欲が異常かどうかを調べるために、
「何を食べても砂を噛んでいるように感じる」
「食べなければいけないので無理に食べている」
などの訴えがあるかどうか、あるいは
・ズボンのベルトの穴がひとつ進んだ
・風呂へ入るときやつれていることに気がついた
・周囲の人からやせたと言われた
などがあるかどうかを聞いてみることは有効です。
具体的に標準体重BMIという基準があります。
BMI=体重(kg)/(身長(m)x身長(m))
18.5未満:やせ
18.5-22未満:標準
25-30未満:肥満
30以上:高度肥満
これを基準にまずはチェックしてみてください。
ここでは摂食障害を主に取り上げます。
(1)拒食症である神経性無食欲症は
1.標準体重の85%以下である
2.体重が不足していても、肥満へ対しての強い恐怖がある
などの症状が見られます。アメリカの兄弟デュオグループ「カーペンターズ」のカレン・カーペンターが拒食症で命を落としてからこの病態が大きくクローズアップされました。
神経性無食欲症の病型は2種類あり、
a.もしくはむちゃ食いしたあと吐いたり下剤を使って排出する(むちゃ食い/排出型)
b.むちゃ食いも排出もしない(制限型)
(2)過食症である神経性大食症は
1.朝昼晩の3食以外に、それ以上の量をたべる。そして食べていることをやめることができない。
2.むちゃ食い(大食発作)が週2回以上3ヶ月にわたって起きている
などの症状で、病型は2種類あり、
a.むちゃ食いのあと吐いたり下剤を使って排出する(排出型)
b.むちゃ食いのあと過剰な運動や絶食をする(非排出型)
これら2つの症状は行動面や心理面においては表面的には違いますが、どちらも心因性の同じ根っこの疾患です。心因性というのは、摂食障害になっている理由が了解できるという意味です。
摂食障害の方へのアプローチは色々あります。これ!という1つのセラピーではなく、色々試していかないといけないところに、この疾患の取り扱いの難しさがあります。
色々なセラピーがありますが、どれもやり方は同じです。クライエントさんに、距離を置きながら、しだいに距離を縮めていく作業が必要とされます。この相反する作業をしていくのがカウンセラーの役目になります。
このへんがあるために摂食障害はカウンセラーの技量を問われる疾患であるといわれる所以(ゆえん)なのです。
摂食障害については、M.バリントのharmonious mix-up(調和渾然体)というセラピストの在り方、あるいは家族療法が比較的よく効く療法です。
harmonious mix-upとは、患者にとって空気のような存在になるということです。つまりもしそれがないと生きていくことはできないのだが、それがあることは意識することもない、という状態です。
こんな依存状態にしていいの?と思われる人もいるかもしれませんが、人の自立ということを考えた場合、自立するには、まず依存が必要です。たっぷり依存する中で自立が育っていくのです。
依存とは甘えです。昔の日本はこの甘えがあった。今の日本はそれが希薄です。西洋はもともともっと希薄です。西洋に摂食障害が多い理由、家族療法が盛んな理由はこのへんにもあるように思います。
西洋の教育は小さい頃から両親とベッドを別にされ、個人主義でバンバン鍛えながら育てていきます。真に甘えることを禁止され、大人にされた子どもはいつまでたっても子どものままです。
マナー的には大人を仕込まれているので見た目には随分老成しているように見えますが、内心はびくびくしている子どもです。日本人にはマザーコンプレックスが多いと言われますが、欧米はそれ以上に多いです。それも病的な人が多い。(国の名前はあえて出しませんが)
摂食障害について何を書こうかと迷っていたら、下坂幸三の「心理療法の常識」という本によい文章がありました。今回はその一部を全文紹介します。ここでは摂食障害だけでなく不登校や非行や引きこもりのことも書いてありますが、それはみんな根っこが同じだからです。
「子の苦労」という部分からの抜粋です。この前に「親の苦労」について書かれていますが、興味のある人は是非手にとってお読みください。子どもから親への過剰すぎる期待について書かれています。下坂は、もう亡くなりましたが、摂食障害に関しては第一人者の方でした。
「子の苦労」
さて子の苦労に移ろう。ここでは、ご存知の「親に手をかけなかったよい子」の苦労について主として解説しよう。
こういう子どもたちは、ごく小さい頃から親の苦労を敏感にとらえ、家庭の状態をよく読み取ることのできた、けなげな子どもたちであったと思われる。
姑・小姑問題に悩む若い母親の愚痴のよき聴き手であったり、病気がちのほかのきょうだいの手当てに忙殺されている親の姿をおとなしく眺めていたり、成績が悪かったり不良化したりで親にさんざ手をかけるきょうだいの姿をみて、自分は親に迷惑をかけまいと心中にちかったなどの子どもたちであったといえよう。要は大人たちの顔色を八方うかがいながら、自分の言動を大いに制限してきた子どもたちといえよう。したがって親に手をかけないためのおのずからなる苦労、苦労をおもてに出さない苦労を幼時から重ねてきたとみられる。
そんなしだいで、彼らのなまの感情や欲求は、ほとんど親には伝達されない。当然、幼時期から漠然としたさみしさや不満をかか、を」むことになる。
この手のさみしさや不満をおおい隠してくれるよい手段は、やがてひとつのことに熱中していくことである。それが学業、スポーツ、稽古ごとなどであるなら、親からも大いに支持されよう。この場合は典型的な「よい子」になる。
親から歓迎されない一事への熱中としては、テレビ、ビデオ、ファミコン、その他のゲーム、モデルガン、マンガなどへの熱中が挙げられよう。これは親からは好まれない熱中だから、いずれ自室にこもりがちになるだろう。
親から歓迎されるにせよそうでないにせよ、かたちにあらわれたものにすがり、これを自分の安心の拠り所とする点では、それは共通している。かたちにすがるのだから、もろもろのかたちはくっきりとして大きく高くあらねばならぬ。学科の点数なら百点がよいわけだし、モデルガンなら百丁そえてもまだ足りないということになる。
しかし彼らなりの懸命の努力により目前にあらわれたかたちが、このたびは自分の期待を満たしてはくれないと自覚したとき、それは彼らにとっては深刻な挫折感となる。成績が一番から二番に落ちても、将来ピアニストになることを夢見ていて練習にはげんできたが、新しい教師からとてもプロにはなれないと宣告されても、母親からこっそりモデルガンを一丁捨てられても、いずれも深刻な挫折体験となりうる。自分の拠り所が一挙に失われたと感じられる。
それは薙針盤を失った船、錘をおとしてしまった船にもたとえられよう。このとき以後、彼らは、新たなる拠り所をさがしてさらに迷走を続けることになる。
この新たな拠り所さがしは、子どもたちにとっては、やはり大変な苦労なのだが、それはわれわれ治療者ならびに世間の目には適応の失敗として映ることになる。それは不登校、昼夜逆転、一層の自室への閉居、ステレオの鳴らし放し、極端なダイエット、過食などといった内向きの拠り所さがしから、夜遊び、異性交遊、暴走族への仲間入りなどの外向きの拠り所さがしにまで及ぶ。しかも、この内向きと外向きの迷走がしばしば混り合う。
しかし右のような新しい拠り所は、一時の糊塗にすぎないことは、本人もうすうす自覚している。それ故に、心中のよるべなさ、むなしさはつのるばかりである。真の拠り所は、家族の中に、親と子の触れあい以外にないことが、究極には彼らに感知されるようになる。
しかし、彼らが親との感情交流をふたたび求めるようになるといっても、それは、からみつきしがみつくような愛情希求であると同時に、必ずうらみといかりを伴っている。しかも親へのからみつきは幼児のそれに近くなる。外見には、「よい子」から一挙に「わるい子」へと転換する。
こういう状態に陥ると、自己の幼児期のつらい暗い記憶が鮮明に浮かび上るようになる。心理療法を受けていれば、この暗い記憶は一層はっきり浮上してくる。当然、親をうらみ責めるようになるが、それは親にとっては、たいてい寝耳に水である。つまりよい子であらざるをえなかった苦労話とうらみとが語られるようになる。それは当人の回想としてはもとより真実であろうが、いかに感受性が鋭いといってもしょせんは幼児の体験である。家族の置かれていた困難な全状況が把握されていたはずはなく、彼らの心中に現出した回想は、状況の、そしてコンテキストの部分的切り出しにすぎない。それは舞台の暗転にも似て、ときには時の流れにより、ときには両親の知恵により、さらには治療者の適切な介入によって、舞台はひと回りして、やがてまた日が射してくるようなものである。
家族療法、あるいはごく最近、釆目した家族療法の大御所ライマン・ウィンのとなえた家族コンサルテーション、ここでいうところの「家族への援助」は、これまで粗描してきた親の苦労と子どもの苦労とを束ね合わせて、同時に解消してゆこうとする試みである。
患者とその家族とを切り離すことなく、同時に援助していくことが、自然な無理のないかたちの「治療」であることは、大方の納得されるところであろう。むしろ従来の個人中心の治療のほうが、人工的で不自然なものであった。
しかし、われわれは、その不自然さになれきっていたために、患者とその家族とを別つことなく援助するという家族療法の手法が、かえって不自然に映るという、さかさメガネを長い間かけ続けていたのではないだろうか。