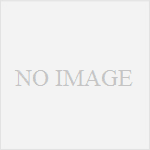認知行動療法という心理療法のことは聞いたことがあると思います。ときには認知療法とも言います。だいたいどちらも同じことを言っています。
大雑把に言ってしまえば、患者の考え方の偏りを修正するためのカウンセリングです。
認知行動療法の歴史をひも解くと、考え方の偏りを変化させるために、どういう技法を使うのかによって、3つの時期に分けることができ、認知行動療法を発展させてきたのおひざものアメリカでは、現在第三期に入ったと言われています。
認知行動療法は1970年代頃から、アメリカの病院などクリニックで使われ出しました。
人は意識せずに自動的に、その人特有の考え方や感じ方をする。それらをスキーマと呼ぶ。そのスキーマは幼少の頃から培われたもので、スキーマに歪みがあると、その思考や感情のクセによって生き辛さを生み出してしまう。抑うつ感や不安などを起こしてしまう。このスキーマを変えることによって患者さんの症状は改善する。
この理論によって自分の感情を日記のように書き出してその思考の歪みを自分でチェックする自習帳などが用いられました。
現在、日本のクリニックなどで用いられている認知行動療法は、このアメリカの第1期の方法です。なぜ、第2期、第3期の方法が用いられていないのかと言うと、それは第2期、第3期の方法は、効果的ではあるのですが、カウンセラーの素質と負担が大きいからです。クリニックでは医者が認知行動療法をすることも多いです。お医者さんは薬物療法の大家ではありますが、心理療法の勉強や訓練を時間をかけてやってきているわけではありません。次に述べる第2期、第3期の方法は、心理療法の訓練が必要とされる方法なので、なかなかお医者さんとしては手が出せないのかもしれません。
さて、認知行動療法が世にでてからは、他の療法にひけを取らないほどの効果を上げ始めてはいましたが、それが処方できる患者さんの範囲は限られたものでした。つまり思考のクセを取るだけでは症状が改善していかないことに気がついたのです。そこで、従来のスキーマを変える手法にプラスして、幼少の頃の体験を再体験させて感情を解放する手法が取り入れられました。(この手法は特別な訓練が必要なので、ここでお医者さんにとって手に余るものになったのでしょう。)自分にとって重要と思われる人物を目の前に想像してもらい対話する方法や、自分がある人物の役割になりきるようなセラピーが併用されたのです。また患者さんのイメージを扱う、催眠イメージ療法的なアプローチも取られました。
ここで重要なのは、カウンセラーが患者さんの親の役割をすることです。親代わりと言っても、なんでも受け入れることはできないので、ある限られた範囲になってしまいますが、それでもしっかりと患者さんへ親代わりの愛情を与えることをするわけです。ちょっと専門的に走ってしまいますが、これは児童精神科医のウィニコットの言う「ホールディング」でもあり、精神科医バリントの「調和渾然体」、ハコミセラピ-の創始者ロン・クルツの Loving Presence(愛と共に存在する) の態度そのものです。つまり、ここで認知行動療法は「認知」を超えるものを扱うようになったわけです。
これは、しかし、自然な流れだと思います。考えだけが変わっても何も変わらないということは日常よく見聞きすることですし。
次に、認知行動療法は、驚くことに「禅」のアプローチを取り入れます。これが現在の第3期につながってきます。キーワードは「マインドフルネス」という瞑想です。これはサンスクリット語の英訳で、原典では、サティと言います。マインドフルネスについては、メルマガやサイトの記事で述べていますので、そちらをご参照ください。
このマインドフルネスによって患者さんが自分で自分を改善するための基礎体力をつけることができることに認知行動療法家が目をつけたわけです。
マインドフルネスがアメリカに伝えられたのは1960年代の鈴木大拙に始まります。日本の禅僧である大拙はアメリカに衝撃と共に熱狂的に受け入れられました。1970年代になるとベトナムの禅僧、ティク・ナット・ハンがそのバトンを受け取り、それが1980年代始めにストレスクリニックを開いたカバットジンへ受け継がれます。
現在第3期に入った認知行動療法は、境界性パーソナリティ障害(リネハン)やうつ病(シーガル/ティーズデール)へのメインアプローチとしてこのカバットジンが経験的に積み上げたマインドフルネスのスキルを利用して大きな成果を上げています。マインドフルネスを活用しながら一方で認知の歪みへも執拗(しつよう)にアプローチしているのが現在の認知療法です。
うつ病へのアプローチとしてのマインドフルネス認知療法はマニュアル的には目新しく目に映りますが、やっていることはカバットジンの手法そのものと言ってもいいかもしれません。それほど彼の手法は完成されたものだということです。
(当センターで行うマインドフルネス認知療法は、このシーガル/ティーズデールの方法とは異なっています。認知の歪みに対しては、さほど重要視していません。それよりも認知を覚醒させるおおもとになっているこころの原風景へのアプローチを重要としています。クライエントさんと世界とのつながりの根っこを見ていくセラピーです。)
しかし、このマインドフルネスですが、これはスキルではあるけれど、スキル以上のものでもあります。もともとお釈迦様が最終的に到達したとされる解脱のスキルですので、人生を生きる哲学でもあるのです。認知行動療法は、マインドフルネスへようやく到着しましたが、まだ認知の歪みというスキーマ問題に始終しています。つまりなんとか躍起(やっき)になって思考を変えようとすることに挑戦しているわけです。マインドフルネスと認知の歪みを変えるということは、相反する事がらなのだと、私は思いますが、そのへんを認知療法家の方々はあまり真剣に考えられていないようです。
先にあげた境界性パーソナリティ障害の患者さんに使われているリネハンの弁証法的行動療法もメインはマインドフルネスのスキル習得としながら、なかなか認知の歪みという呪縛から逃れることはできていないのです。そうは言うものの、弁証法的行動療法も大きな成果をあげている事は事実です。これはマインドフルネスがいかに有効な技術であるかを示していることに他ならないと思うわけです。(認知療法家の人は、そうではない、やはり思考の歪みへ挑戦することも重要だ、と言うかもしれないけれど。)
一気にマインドフルネスへ突き進むと認知行動から大きく外れていくことに危惧される専門家もいるでしょう。しかし、専門家の中にもそれをわかっている人も居ます。認知行動療法を始めたのはベックという人ですが、そのベックと私信を交わしたウォルシュという人が彼の書籍の中で、次のように書いています。(原文そのままでなく、分かりやすく簡略化して紹介します。)
スキーマを修正しようとする試みは認知療法的なアプローチだけでは十分な成功をおさめられない場合もある。自傷者やトラウマのサバイバーに対しては不可能と言ってよい。これは認知療法の限界を示すものであり、頭で理解はできるが自分自身に関する根深い確信を変えることはなかなか容易なことではないのである。このような場合、技法以前のこと、つまり基本的な治療関係が重要となってくる。これは実証的に検証困難であり、認知療法家はこの手のことを技法とは見なさないかもしれないが、確かにそれがないと完治はしないのである。
私はこの関係を「治療の贈り物」と言っている。これはセラピストとクライエントが治療過程において、お互いに分かち合い、ともにくぐり抜けてきた、「肯定的な生活を維持させる何か」から成り立っている。この、人を精神的に生き返らせる効果によって、クライエントは、何かを受け入れて、それを手放すことが可能になるのである。つまり、治療転機における重要な鍵を握っているのは、技法の彼方に霧につつまれて存在する、スピリチュアルな相互の関係性のなかにあるのである。(自傷行為治療ガイド, Walsh, B.W., p.189-p192)
ちょっと難しい引用かもしれませんが、ウォルシュは治療を進める上でのスピリチュアルな関係性、つまり霊性ですね、そいつが認知療法でも必要だと感じ取っているのです。この考え方はマインドフルネスと実に親和的な方向性です。
リネハンやシーガルが無自覚的(?)にマインドフルネスのスキルを導入しているのに対してウォルシュはマインドフルネスの本当の意味をわかっているのだろうと思います。彼の言っていることを静かに聞いてみると、そこから自然と認知行動療法の次に進む道=霊性への回帰、が示されているように思います。
霊性とは、ホラーや前世や憑依とは次元が違うものです。人間の生き方そのものであり日常的なものです。(霊性については、別記事で書かせていただきます。)そう考えると、認知行動療法の行く末は、ほとんど他のセラピーが目指すものと大差はなくなってくるような気もします。色んなセラピーが一つの和を作って丸くなる、そんな感じでしょうか。