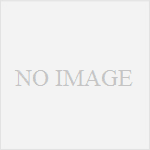腐っていることは癒しです。それは生きていくためのチカラとなります。
懐かしいにおいは安心・安全基地へつながる道しるべです。その中でも、腐った腐敗臭というものは、もっとも深いにおいといえるでしょう。胎児のときに経験しているにおいだからです。
家族療法のボーエンは、自己分化(ディファレンシエイト)の重要性を説きました。自己分化とは簡単に言うと、自分で自分を癒せるようになるということ。
これは対人関係において最も大切な尊い行為です。自分でトラウマを癒す原動力となります。自己愛撫、この最も尊い行為の底のほうにある感覚が「腐っていく感覚」です。腐る(腐敗)ということは、生命体において、なくてはならない現象なのです。
腐るということ
私は中学2年のときに、三重県の片田舎、四日市から大都会の横浜へ転校しました。横浜へ移って思ったことは、四日市への郷愁です。あの頃はよかったと思っていました。若くして昔を懐かしむということは、自分に老成趣味があったのだと思っていたのですが、実はそんなことではなかったことに気がついたのは、ずいぶん後になってからです。確かに中学の頃から禅寺や山へ1人でよく行きました。渋谷へ遊びに行くよりも多かった。それには理由(わけ)があったのです。
中学2年で「あの頃はよかった」と思うのは、たぶん不幸なことです。私は引っ越し先の横浜をどのような目で見ていたのでしょうか。それは次の3つのことに象徴されています。
(1) アスファルトで道が固められている
(2) トイレが水洗である
(3) 特殊学級がある
□循環系
四日市では幹線道路はアスファルトでしたが、路地や車1台が通りそうな道はまだ土でした。道が土であるということは、生態系が循環するということです。雨が降れば土にしみ込む。葉っぱが散れば朽ち果ててたい肥になり土が肥える。肥えた土には風で飛ばされてきた種が根を張り作物が実る。この循環系です。
しかし横浜では、がっしりとアスファルトで地面が固められていました。玄関を出ると、すぐに道があり車がスピードをあげて通り過ぎます。そこには余裕がありません。息苦しさだけがあります。息苦しいということは「生き苦しい」のです。生きていくのがむずかしい。ある人はマニュキュアを塗ると爪で息ができなくなって苦しいと言っていました。それも同じことのように思います。
この循環系をニーチェは永遠回帰と呼び、宮沢賢治は農業指導の実践でこの世界を捉(とら)えました。こころの治療の視点から循環系を捉えると、人のこころの奥底には、このような肥沃な土地があるのです。
カウンセラーは、相談者のこころの内にはそのような肥沃な土地があることを示して農業指導をする人です。その土地を耕して収穫するのは相談者の方、本人です。
このことに気がつくまでは時間がかかりますが、カウンセリングが進んでいくうちに、この約束の地ともいえる肥沃な大地は、ときおり相談者の方の日常や夢の中に立ちあわられてくるようになります。最初はかげろうのように一瞬垣間見ることができるだけですが、農業指導が進むうちに自分の足がその大地の上に立っていることに気がつき始めます。素足が大地にしっかりとついていることに気がつきます。そして循環系を生きるようになります。永遠回帰です。
□におい
横浜の家は父親の会社の社宅でした。4階建てのアパートの4Fで景色は良かったです。東海道新幹線や富士山が見えました。そしてトイレが汲み取り式から水洗になりました。これまでのようなくさいにおいのする汲み取り式のトイレではありません。大便と小便の入り混じったにおいのする肥だめがなくなったのです。私の体内から排出された糞尿は即座に水と一緒に下水道へ運ばれてしまいました。私の生活からあの懐かしいにおいがなくなったのです。
人間に限らず生命体にとってにおい=嗅覚というのは、かなり根源的な領域に属しています。視覚や聴覚は新しい脳である前頭葉が処理していますが、嗅覚はもっと古い脳である大脳辺縁系が処理しています。ですからにおいについては当然懐かしさの度合いが違います。頭で反応する懐かしさではなく、体が反応している懐かしさです。
鮎(あゆ)がなぜ自分の生まれた川へ戻ってこられるのかというと、彼らは自分のにおいをかぎながら戻ってくるそうです。犬や猫も鼻が利(き)きますね。嗅覚というのは視覚よりも根源的なものをもっているということでしょう。
自分のオナラのにおいを嗅ぐのが好きな人います。タレントの小倉優子も自分のオナラのにおいが好きだと言っていました。私も周りに人がいなければ、椅子に座ってオナラをしたときはにおいをかいでみます。かぎながらうっとりとします。自分の座っていた椅子へ鼻をつけてオナラのにおいを嗅いでうっとりしているわけなので、ちょっと他人が居たらできないことです。絶対に引かれてしまいます、変人です(笑)。
汲み取り式のトイレのにおいはくさいですが、すぐ慣れます。汚いですが懐かしいにおいです。水洗トイレは清潔だけど冷たい。昨今の除菌グッズは生命力(懐かしさ)を殺ぐ(そぐ)道具にすぎないように思います。
指しゃぶりや爪かみが大人になっても治らない人がいます。あれは治さなくてもいいのです。子どものころ、親の愛情が足りなかったわけではありません。実際、指しゃぶりをしていると安心するでしょう。実は指は、おっぱいの代理ではないのです。
それは胎児のころの羊水に混じる腐った感覚を思い出すからであり、懐かしいにおいにつながっていくからなのです。人は胎児のとき、腐った環境と交流しながら育っているのです。精神科医の石川憲彦は、このにおいを「おうちのにおい」と表現しています。彼は外耳炎になった耳ダレを指にとってにおいをかいでいたそうです。その腐ったにおいを「おうち」と表現しています。おうちとは子宮のことです。スピルバーグの映画のE.T.が空を指さしてつぶやくシーンが目に浮かびます。E.T.も「ホーム」(おうち)を探していました。
胎児はへその緒を通して母親から栄養や酸素をもらっています。老廃物は羊水に放出され母親によって外へ除去されますが、少しは羊水に放出されたうんちやおしっこを胎児は飲み込みます。羊水の中の胎児は、糞まみれになりながら、海に浮かんだ気分でぼんやりとしているのです。この老廃物、腐ったものと渾然一体になっている記憶、これらは大人になっても感覚的に残っているのです。それを思い出す行為が指しゃぶりや爪かみ。ですから、指しゃぶりなどは良いクセなのです。(不安が原因でしゃぶる指しゃぶりはクセにはなりません。不安が去ればすぐなくなります。)
懐かしい腐ったにおい。オナラはそのものですね。自己臭恐怖という症状がありますが、これは見方を変えると「自己臭興味」という健全さです。自分のにおいに帰るのです。自己臭恐怖は重篤な妄想を伴った病態へ進行する可能性があると言われます。その自己臭恐怖を、腐ったにおいを介して自己臭興味に変えてしまうのが、私の治療戦略の1つです。
鼻くそも腐ったものへつながります。子どもでよく鼻くそを食べている子がいますが、やめさせる必要はありません。あれも指しゃぶりやオナラのにおいをかぐのと同様に、腐ったものへの郷愁があるのです。
私は、鼻をかんだとき、べとべとした鼻汁の中に少しかたまった部分を見つけたりすると嬉しくなります。その固まりを手にとって指をこすり合わせているとだんだんと固まって鼻くそ団子が出来上がっていきます。あのときの感覚はとても充実しています。粘土をこねているのと全く同じで、いやそれ以上にさまざまな感覚が動いています。粘土をこねるくらいなら、自分の鼻くそをこねていたほうがいいくらいです。そしてまるめた鼻くそが出来上がると、次は爪で小さく切っていきます。この作業を通して精神が安定していきます。
子どもも大人も大いに鼻くそ丸めの作業を楽しむと良いのです。私は小学校に入るまで蓄膿症気味だったせいもあり、ハナタレ小僧でした。鼻の下に垂れた濃厚な自分の鼻汁を使って鼻くそを作る名人でした。においと安全基地については関連記事を参照ください。
□チック
私は、爪かみやおしゃぶりはないのですが、その代替行為かどうかはわかりませんが、くちびるを合わせて音を出して楽しむクセがあります。10代からやっていて今も抜けません。よく注意して他の人を観察しているとわかりますが、このクセは結構残っている人がいるんです。くちびるから音を出すとき顎を鳴らしたりして楽しむこともあります。私の密やかな楽しみです。
私のくちびるを使う楽しみですが、これは精神医学的にはチックと言えます。以前、精神分析が盛んな頃は、チックやアトピーなどは心身症であり、子どもが母親や家族に対して不安を抱いているからだと言われたものです。
しかしそこには科学的根拠は何もないのです。証明されているわけでなく、母親との関係が改善してきたらチックが治った、だから母親との関係が原因だろう、という仮説にすぎません。(仮説なのですが、一部やはり母子関係が影響しているものもあるので、それがすべての原因のように広まってしまったのです。)
私が自分のチックも含めて経験上感じていることは、これは子どもと外界との関係による心因ストレスが関与している可能性はあるが、それは母子関係というより、子どもと社会との関係のほうが大きいのではないか、ということです。つまり子どもが抱く社会への不安あるいは期待が表出した行動の1つなのです。しかしこの不安は、健全な不安です。社会は子どもが思う通り、怖かったり期待に応えてくれる可能性のあるものです。ですからチックなどは健全な不安なので、問題にするのではなく、ほっておけばいいのです。
精神科医の石川は、多動やチックのことを、子どもは動くものであるという視点で評価しています。欲求不満や愛情が足らないのではないと言います。危険が迫ってきた場合すぐに逃げないと生命を維持できない。その準備を子どもは日ごろから試しているために、大人からみると落ち着かない動きをしていると言うのです。つまり、子どもが多動なのは理になかっている。常にウォーミングアップしているのです。
このような視点で考えると、チックやADHDという現象は自然な子どもの行動であることがお分かりになるかと思います。日本は特に動きを抑える社会です。子どもが飛び回っていたらすぐにオトナシクシナサイと諫(いさ)める。これでは子どもはたまったものではありません。多動やチックは何も悪いことはないのです。
自分でコントロールしてそれらを抑えることは、逆に自分を縛ることになり、本当の自分を見失うことになりかねません。自分が抑えつけられるから怒りが沸いてきてかんしゃくを起こす。私も例にもれず、子どもの頃はかなり多動で手を焼かせたようです。その行動を小学校の先生によって規制されていたので、家に帰るとかんしゃくをよく起こしていたのです。かんしゃくに効くと言われて、家庭の常備薬だった救心を飲まされていました。現代でいうと、覚醒剤と同じ化学組成をもつリタリン、コンサータ、ストラテラ(ADHD治療薬)などの、向精神薬の処方でしょうか。本当に現代に子どもをやってなくてよかったです。
□嗅覚は許し、腐るのは許し
中間世(死と受精の間)に居る子どもの魂が、この親たちの子どもになろうと決心して両親を選ぶと、受精します。親が望む望まないにかかわらず、受精は子どもの意志によって行われるのです。そして受胎から十月十日たつとこちらの世界へ生まれ落ちます。誕生です。
このとき私たちは圧倒的な視覚の世界へ入ります。この世は視覚と聴覚が優先している世界です。一方胎児の世界は嗅覚と聴覚優先の世界です。においが充満している世界です。自分の糞尿まみれになりながらそれを飲んだりしている世界です。そのにおいが満ちている世界です。
汲み取り式のトイレに入ると最初はクサいと思っても、しばくしたらすぐ慣れます。この感覚は何かというと、それを「許している」という感覚なのです。腐っていくにおいというのは許しなのです。アロマのような調合された素敵な香りではなく、懐かしい腐臭です。
牧草などのにおい、穀物のにおいも糞尿のにおいに近いですね。腐るにおい、そこには許しがあるのです。犬などは相手の肛門のにおいをかいで敵か味方かを判断します。それで味方と判断したら、自分の子どもでなくても、猫やサルにさえ自分のお乳をあげることを許します。あの感覚です。腐っていくにおいというのは許しなのです。嗅覚は許しにつながっている。
見ようとすることは区別すること
これと反対に視覚というのは差別から成り立っています。自分と相手がどう違うのか、そこを問題にしていきます。あれとこれはどこが違うのか、その区別を見つけるための感覚です。視覚は差別につながっている。
新聞などで「子どもが見えない」という表現を見かけることがあります。子どものこころの中を理解できないという意味で使われますが、大人にとって子どもを見るという行為自体、区別しようとする無意識の感覚が働いているかもしれません。
大人になるのは区別ができるようになること、という教育に親しんできたからです。見ようとする、区別しようとするから見えなくなるのです。
見ようとすると、許す行為から離れていきます。差別する方向へ行く。見ようとするのは大人の世界です。大人はかつて子どもであったわけですが、見ようとすることの中には、その懐かしい子ども時代の腐ったにおいの世界からは遠ざかっています。嗅覚から遠ざかっています。あの頃の懐かしい自分、子宮の中で糞まみれになっていた自分を見失っているわけです。自分を見失った大人に子どもの姿など見えるはずはないのです。
□視覚は差別
引越し先の横浜の中学は1学年14クラスあるマンモス校でした。私はそのこと自体にも圧倒されましたが、何か管理されているような気持ちでした。無意識の働きだったのでしょうが、懐かしいにおいを捨ててはなるまいと思ったのでしょう、横浜では関西弁(伊勢弁)で話すことを止めませんでした。私のささやかな抵抗だったのでしょう。
しかし、巨大な学校というイメージよりもっと不気味だったのが、15組の存在でした。15組は1年~3年までを通して1クラスしかない特殊学級(特別支援教室)だったのです。四日市に居た頃は、小学校にも中学校にも特殊学級はありませんでした。できる子どももできない子どもも同じクラスでした。私が15組を知ってから思っていたことは、どうして皆と一緒に勉強しないのだろう、どうして学校は管理するのだろう、ということでした。15組という存在は特別でした。他の14クラスとは明らかに壁があり、そこにはどうしても差別している壁を感じずには居られませんでした。
15組があるということは、普通学級の中には障害児は居ないのです。四日市では居たのに横浜では排除されている。この15組の存在は、ある特性をもった子どもを否定して見ないようにしている社会があるのだ、ということを私に知らせました。私はそれに驚き、同時に東京には住めない、四日市へ帰りたい、という郷愁が募っていきました。そういう背景もあって、大学は東京圏以外の大学を受験しようと、すでに決心していました。
特殊学級を作るというのは普通学級との間に壁を作ることです。そうやって外から見えないようにすることです。壁があるために、そこには秘密が自然と出来上がってきます。このような内側へこもっていくような秘密というものは、その組織自体を融通の効かないものにしていきます。固い人間関係に納まっていきます。自意識過剰になっていきます。当然そこでは暴力も開放されません。
これは現在の核家族のあり方と同じです。秘密のある家族です。このことは外で言っちゃだめだよ。そうやって官能的な気分が外へ向かわずに家族内だけで煮詰まっていく家族。また、この内側へこもっていく感じというのは妄想気分を増長させ、視線恐怖から妄想的な恐怖症状へ悪化させる可能性を秘めているのではないでしょうか。
特殊学級の良さもあるでしょう。しかし、その存在自体は一体何なのか。私たち社会が生み出してきたシステムに過ぎないのではないか。私たちの社会をうまく循環させるために弱者を見捨てていくシステムの1つではないのか、と思うのです。どうしてこうしたシステムを作る必要があったのか。それは誰のためなのか。
できないことを許さない「許しのない」社会
発達障害(アスペルガーやADHD)、学習障害というレッテル貼られた子が普通学級へ通うのは苦痛を伴います。なぜかというと、そういうことは異常なんだ、普通じゃないんだ、それは許されないことなんだ、という社会通念が出来上がってしまっているからです。
ただただ腐っていることが許された昔の時代ではなくなったからです。それは懐かしい過去の時代となってしまいました。重度の障害をもつ子が普通級へ通うのは、あの子はできない子なんだと周りが認めているからそれほど苦痛ではありません。問題は、軽度の障害を持った子が普通級へ通うとき。それは「できる」ことを期待されるから、できない自分を責める。周りもできることを期待する。そしてみんなから浮いていってしまう。自分も、周りも、「できないこと」を許すだけでいいのに、許すことができない社会になってしまっているのです。
これは大人の社会がそのように変化してきたからです。大人の影響が子ども社会へも影響をしている。仕事の現場では「できる」ことが当たり前のように要求されます。それが始まったのは、パソコンが会社へ浸透を始めた1980年代半ばからです。できないことが許されない世界に変容しました。それは1990年代後半のインターネット時代になって加速しました。
そのような「許し」のない世界は子どもの社会へも浸透し始めます。発達障害という概念もそのようなブームに乗って登場してきました。「発達のかたよりは許さないよ」という大人から子どもへの脅しです。発達にかたよりがあるというのは自然なことだし、それを咎(とが)めることなど何もないのに。
学校に行かないということも同じです。学校に行かないと人間として欠陥があるように捉(とら)えてしまう。不登校になると大人はあわててしまいます。それは社会のシステムに外れていると思ってしまうからです。学校に行かないというのは病気でもなんでもなく、社会システムへの抵抗にすぎないのに。抵抗にすぎないので嬌声するべきものではないのです。親としては認めてあげるだけで良い。
そのように見ると特殊学級とか発達障害、不登校、引きこもりの問題は社会的な視点が大きいことがわかります。社会的な視点とは視覚の問題、あなたと私は違うんだよと区別、差別する視点です。できないことは大したことではないのに、それをさも重大なことのように取り上げて、大人も子どもも強迫的に右往左往してしまう。できないことは良い悪いと判断するものではなく、自分も親もその思考から解放されることが、現代において一番求められていることではないでしょうか。できないことは人生を豊かにします。腐っていられるから、許しがそこにはあるから、自分のもっとも古い懐かしい記憶がそこにはあるから、もっとも人間らしいことを体験しているのです。
□核家族

大人の世界がとても小さなものになってしまった、ということも大きいでしょう。それはテレビの影響も大きい。テレビというのは、視覚と聴覚の集大成です。「区別する」という意識の集大成のものです。
私たちはドラマを見てそこに自分の生き方や家族のことを振り返るという習慣が出来上がってしまいました。それは架空のストーリー、星の数ほどあるストーリーの中の一握りの物語なのに、そこに希望を見出してしまう。つまり考え方の視点がすごく狭まったのです。実在しない架空の夢を希求する願望を強化したのがテレビでしょう。夢は実現する、この甘い言葉で実体のないものまで実現可能かのような錯覚を植えつけていくのがテレビなのです。
こうやって視覚重視になって世界が小さくなっていくと、自分とその周りの家族という小さい単位だけで生きるようになり、隣の人と交わしていた温かい生活から離れていきます。懐かしい腐っていくにおい、腐っていることが許された世界から遠ざかります。ほんとうの許しから遠ざかる。
かつて学校や役場は町はずれにありました。そういう辺境の場において社会と交わっていた。そこに行けば社会があった。今はどこへ行けば社会と出会えるのでしょう。人間同士の交流を行えるのでしょう。都心へ電車で出かけても、スマホでSNSに書き込みをしても、個人は個人のまま。情報は豊富にあるのに社会と出会えている気がしません。
家族がどんどんと小さい固まりになっていき、家族を大事にすればするほど、何かの問題が起きると家族の中だけで解決しようとします。これはどういうことになるかというと、家族の中でその問題を起こした責任者探しが始まるのです。そして、こうなったのは親の責任だ、という社会からの目、専門家と言われる人たちからの批判が集まります。こうやって家族内に罪の意識が生まれます。本来なら必要のない罪の意識なのに、家族という単位でしか考えていないと、こうなってしまいます。
親は、未成年の子どもの成長には責任はありますが、社会に対しての責任なんて過剰に考えなくていいのです。専門家は社会を飛び越して、家族にだけ責任を押し付けようとします。子育ての途中では、こんな子なんて捨てたい、こんな子なんて産まなければよかった、そういう気持ちを持つことはあり得る話なのです。そう思いつつ葛藤するのが親の責任です。
家族は安全基地だが、ぶつかり合いもある
核家族内には、刺激的な表現ですが、そのような暴力装置が始めから備わっている傾向があるとも言えます。これを精神科医の斉藤学は、「家族というものは闘争の場である」と表現しています。これを殺意がある、と言ってはいいすぎかもしれません。しかし、それと類似したものがある(ぶつかり合う)のが核家族なのです。昔のアメリカのホームドラマに見られるような家族は、単なる夢物語にすぎません。
では、核家族は安全基地にはなり得ないのでしょうか?そんなことはありません。そこには母性、父性がしっかり根付いており、そこは安全基地に代わりはありません。そうなのですが、ぶつかり合う緊張感が漂っている場であるともいえるでしょう。闘争といっても、安全基地内でのぶつかり合いです。つまり思春期の親子関係ですね。
子どもを育てるということは、親の性格と生活に子どもをマッチさせることです。模範的な親なんてものは存在しません。親は性格を丸出しにして子どもに対応していれば良い。それが育児です。親は自分の思い通りに子どもを育てる、そこにしか親と子の絆は生まれてきません。そうやって喧嘩を繰り返しながら、子どもは思春期を通過して、自分の過去や親と別れていきます。
こうやってお互いの相性を主張しながらぶつかり合って、傷つけあって、家族は成長していきます。親と子の相性など、もともと良いはずはありません。違う人間なんですから。ちくしょう、こいつとは相性合わないな、うまくいかないな、とお互いに迷惑をかけあっているのが家族なのです。
迷惑は他人に対してもかけていいとも言えます。それによって家族内の闘争=暴力がその家族だけで煮詰まることから解放される、社会的に開かれた家族になります。
子どもも、風邪をひいたら他人に移し、また他人の風邪ももらってきて熱を出す。そのような迷惑の掛け合いがいいのです。そこには循環系があります。悲しいこと怖いことを家族の中だけで処理しようとしないことです。外の社会に対してそれを出していく。うちの家族はこんなにイビツなんだよ、子どもをこんなに殴ってしまうんだよ、ということを外へ出していく。
家族にはそれぞれその家族特有の歴史があります。斎藤はそれを家族神話=家族ロマンと言っています。例えば、うちの祖父は歌舞伎役者のような美形だった、母親の家系は日本舞踊の名取である、父親家系は医者の家系である、そのような神話=ロマンです。石川は、このような神話を「エロス」と呼んでいますが同じことでしょう。
このような神話、ロマン、エロスに捕(つか)まってしまって、そこから動けない状態になっていることが、家族の中に事件を生み出していくのです。これらの神話は別のストーリーに書き換えていかなければならない。
そのために、家族という暴力システムに風を入れる必要がある。家族の中ばかりを見るのではなく、家族の外を見て、社会の中の家族という視点で捉(とら)えなおしてみることが必要なのです。家族内で捕(とら)えられてしまっているエロスは外へ出ていかないといけない。
ひとたび社会へ視点を移すと、人間というのは社会の中で迷惑をかけあって生きていることがわかります。そういうことが自然と出来ていた場所が戦前まで存在していた長屋です。懐かしい臭いにおいの漂う場所です。いま長屋を見ることはほとんどありませんが、他人と迷惑をかけ合うということは、長屋モードへの回帰であると言ってもいいでしょう。核家族が「核」でない家族へ開かれていくことなのです。
□虐待と家族

家族というのは、もともと闘争の場であり暴力装置でした。ですから、そのような場で行われる子育てというものは、親が自分の思うように子どもを育てること以外にありません。育児に自信があるとかないとかいうことは関係ありません。親と子が互いに傷つけながら一緒に成長していくのです。
子育てとは親も一緒に成長することだと言われますが、それは、親が自分の思うとおりに子どもを育てることで、親子の闘争に火がつき、親も火だるまになりながら必死に子どもに向き合うことで親が成長するということなのです。この闘争過程で親子の絆が生まれてきます。かけがえのない親子関係が生まれます。
手塚治虫の火の鳥は、燃える炎の中で燃え尽きながら新しい自己を生み出して飛翔していきます。まぁ人間は火の鳥に比べようもありませんが、親の成長というのもそのようなものとも言えるかもしれません。
殴られて育つ子どもは「この親はどうしようもない親だ。憎くてしかたがない。」と思います。「いつか殺してやる。」とも思います。そう思いながら絶ちがたい愛着を感じています。こんな最低な親なのにどうしてこんなに求めてしまうのだろうと思います。この背反する二つの気持ちを持っていることは自然なことです。自然な子どもの感情です。こう思えない子どもがいたとしたら、それは自分の気持ちにしっかりと蓋をしているのです。いい子を演じようとしているのです。だから子は苦しい。
「どうしようもない最低の親だ」という自覚
このように子に思われた親のほうはしかたがない。そういうことしかしてこなかった悪い親だから、思われてもしかたがない。ただ、親にできることは、自分は悪い親なんだと自分を許していくことです。これは居直っているのではない。「こんなに言うこと聞かない子どもだから殴ってしまう。もういい加減にしてほしい。あんな子はどうでもいい。」この気持ちを自分に許していくことです。そして「自分は悪い親なんだ」と自分に降参することです。子どもから暴力を許してもらっているわけなので、親は子どもに甘えているわけです。自分は子どもに甘えているんだな、子どもに育ててもらっているんだなということを自覚していく。この自覚によって、親は、子どもに恩を返していけるのです。
親が、いい親を演じることから降りる。カッコつけないで生きる。世間体を気にせずにワルを出していく。そして悪い親だから、世間並みになるんだよ、なんてことは子どもには当然期待しません。他の家庭と比べることなく、自然な感情を子どもに対して発露しながら生きていく。子どもも「親の期待」という縛りがなくなるので自分を自由に表現できるようになります。
このような親子関係は、周りから見ると波乱万丈に見えるかもしれませんが、感情はまっすぐに伝わりあっています。育児書をいくら読んでもこのような関係にはなれません。生身の感情を出し合う親と子の関係そのものが育児書なのです。
いい親を演じようとすると、愛しているというメッセージを送ろうとしてしまうと、それは親にとっても子にとっても窮屈です。不幸です。いい親がいい子どもを演じさせるからです。だから子どもをのびのびと育てるにはいい親を降りることが大切なのです。
児童虐待が問題になるケースは、親に発達の問題がない場合、「いい親でいたい、世間体が気になる」という親の側の自己愛の問題が大きいのです。本当はたいした親ではないのに、「自分は悪い親にはなりたくない。世間からいい親と見られたい。オレ様が一番でいたい。」という親側の身勝手な自己愛によって殴ってしまうところに問題が生まれるのです。親が本当に「自分はたいしたことのない親なんだ。悪い親なのだ。私は最低なやつだ」と自覚できるかどうかです。
これを自覚した親は強いですよ。この覚悟がある親から殴られて育てられた子どもは、親から深い愛情をもらうことになります。なぜなら、殴ったとしても、殴る直前までは怒りの鉄拳でも、体に触れる瞬間、鉄拳が緩み、スピードも緩み、急所を外します。周囲から見ると殴っているわけですが、親と子どおしは殴り合っているのとはちょっと違う感覚があります。
そこには親の子に対するいたわりが生まれています。同時に子は、親に愛されている気持ちを受け取っています。このような感覚で殴ることは、決して悪いことではないのです。子どもに対して演技ではなく生身の感情でぶつかっているので、子どもにも感情がまっすぐ伝わるし、親と子の親密さは逆に増します。
また自分のことが悪い親だとわかっているので、救援を第三者に対して求めることも躊躇しません。それを秘密にしたりしません。恥ずかしがらずに周囲に告白します。そして必要なら裁きも受けます。この行動が大事なのです。
家族のなかだけで秘密をつくらないこと。自分は悪い親であることを自分に許して、子どもに対して向かい合い、世間に対してもさらけだす、これが開かれた家族です。外の風を家族の中に入れられるくらい懐の深い家族がそこにはあるのです。
家族はもともとは暴力装置なので、外の風を入れることは極めて大切なことなのです。脱「核家族化」です。事件は圧力釜のような密室化された家族の中で起こります。家族神話(呪い)、家族のエロスが家に閉じ込められて広がっていかないことが原因です。風通しのよい家族には事件は起こる要因がないのです。
虐待する親は、自分のことを悪い親だとは認めたくない人なのです。これは了見の狭い考え方です。人は自分のワルさ加減、えげつなさを自覚してはじめて生身の人間関係を作ることができるようになるのです。家族というのはもともと暴力装置であるから暴力を回避することはできないのですが、その暴力が虐待になるのか愛になるのかの分かれ目が、親の側のこの自己認識にかかっているのです。
自分のえげつなさを認めると…
自分のワルさ加減やえげつなさを認めていく、許していく。これは何も親子関係に限ったことでありません。
うつ病や強迫性障害の方は完全を求めます。完全でないと、頑張っている自分でないと、自分を許すことができない。けれどこのような方々が相談の中で自分のワルさ加減やえげつなさに気づいていかれると、これまでと違う自分に出会います。
幼い頃から押し殺してきた自分、怖いよーと叫びたかった自分、そのような影(シャドー)として自分の中にあったものに気がつくのです。あぁ、自分ってこんなにビクビクしてたんだ、こんなにワルなところがあったんだ。そして、これも自分だったんだと気がつきます。
これまでの表面的な、社会的な自分がいったん死んで、新しい自分と出会います。この自分はかなり本質に近い自分です。「嫌だけど仕方ないな、これも自分」と自分を離れて見ることができるようになり、そして自分の中に余裕が生まれます。本音を大切にしながら生きていけるようになります。こころの病の回復はこのように行われていくのです。
江戸時代以前の子育て
最後に江戸時代以前の日本的な育児についてです。
中江によると16世紀に来日したイエズス会宣教師モースの記述には、「日本には子どもを背負うという伝統がいたるところで見られ、婦人も年長の子どもも赤ん坊を背負っており、西洋にみられる児童問題を日本は解決している」とあるそうです。
また19世紀の幕末に来日したオルコックは、「江戸の街路では、はだかのキューピッドがはだかに近い屈強の父親に抱かれている光景が普通に見られる。このありふれた光景からわかることは、日本には捨て子の養護院は必要ないと思われる」と書き記しているそうです。
16~19世紀の西洋では、生まれる子の大半が捨てられ修道院などが引き取って育てていました。また修道院でも性的なものも含めての児童虐待が行われており、西洋では子どもが生きていくのは大変な時代でした。
それだからこそ「育児」という概念が西洋で発達したのでしょう。日本ではそのようなことはあえて言う必要がなかったのです。健全な育児が行われていたところに、明治以降の西洋の育児が逆輸入されて育児がゆがめられてしまった。その文明開化のツケが今めぐってきているのかもしれません。
欧米の文化は、大人が楽しむためにあります。飛行機、レストラン、ホテル、コンサートなど、静かに大人が楽しむためのものであって子どもはやっかい払いされています。子どもを静かにさせることのできない親は、そんなところに子どもを連れだすべきではない、という文化です。大人の社交の場から子どもを排除する文化なのです。子どもは家で留守番をしていなければならない。つまり社会から拒否されている。
それと比べると昔の日本の文化は、子どもと一緒に過ごす文化です。子どもをおんぶしながらあやしながら大人は労働したり観劇していた。大人が赤ちゃんを連れて生活をしているのが当たり前の文化なのです。
残念ながら昭和以降の日本では仕事場からは子どもがしめ出されました。朝晩のラッシュの電車に幼い子どもをつれたお母さんが乗り込もうものなら異物を見るような目を向ける現代です。確かに仕事場に幼児が遊んでいると秩序が乱れますし、ラッシュの電車は幼児には危険です。現代は頭を使う仕事が多くなったこともあるでしょう。
しかし、このように子どもを締め出すことによって、幼い子どものいる母親は自分の家の周りでしか生活できなくなっているという現実があるわけです。行動半径がすごく狭い。このへんは、昔の日本の育児を再考してみる価値はあるのかもしれません。
アメリカの文化人類学者ベネディクトは、第二次世界大戦中の日本を研究しました。その中に、日本では自由にふるまえるのは幼児期と老人期であり、欧米では青年・成人期である、と記しています。これはなかなか面白い考察ですので引用してみます。
日本では赤ん坊と老人とに最大の自由と我儘とが許されている。幼児期を過ぎるとともに徐々に拘束が増してゆき、ちょうど結婚前後の時期に、自分のしたい放題のことをなしうる自由は最低線に達する。この最低線は壮年期を通じて何十年もの間継続するが、曲線はその後再び次第に上昇してゆき、六十歳を過ぎると、人は幼児とほとんど同じように、恥や外聞に煩わされないようになる。
アメリカではわれわれはこの曲線を、あべこべにしている。幼児には厳しいしつけが加えられるが、このしつけは子供が体力を増すに従って次第にゆるめられてゆき、いよいよ自活するに足る仕事を得、世帯をもって、立派に自力で生活を営む年ごろに達すると、ほとんど全く他人の撃肘を受けないようになる。われわれの場合には、壮年期が自由と自発性の頂点になっている。年とってもうろくしたり、元気が衰えたり、他人の厄介者になったりするとともに、再び拘束が姿を現わし始める。
(ベネディクト, 1967, 菊と刀―日本文化の型)
現代の早期教育や老人介護問題山積の日本はどうでしょうか。幼児期も青年・成人期も老人期も人生全般にわたって自由が奪われているのではないでしょうか。こんな状態では、うつ病や神経症になってしまうのも無理からぬことではないでしょうか。だからせめて欧米並みに青年・成人期は自由にふるまいましょう。子育て真っ最中の親御さんは自分の好きなように子育てをすればいいのです。
人間的なものは、社会の風習や文化と相性の悪いものがあります。その1つに一夫一婦制という社会制度や子育てがあるように思います。
江戸の父親に抱かれた子どもの光景から西洋人は父性を見るかもしれません。それは19世紀に父性、母性を言い出したフロイトの影響が大きいでしょう。フロイトの功罪と言えるかもしれません。われわれカウンセラーを含めて、心理学者はそれに追従した。
しかし元来日本には、父性も母性も家族愛もなかったとも言えるかもしれません。あったのは、「自分の思うとおりに育てている親たち」なのです。そのように親が子を熱心に育てながら、親は子に育てられてもいるんだ、ということを親は理解していたのです。

参考図書:
こどもと出会い別れるまで-希望の家族学(石川憲彦)
「家族神話」があなたをしばる(斎藤学)
日本人の子育て再発見(中江和恵)