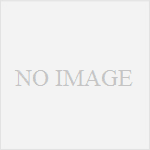思春期の時期は人によっては、長い人もいます。おおよそ、10歳~25歳くらいでしょうか。最近は思春期が長くなっているようです。
□サリンジャーは、思春期の小説
サリンジャーの「ライ麦畑でつかまえて」を読んだのは16歳の夏でした。これまでの人生観が反転し、クラクラとしながら、憂うつの底へ突き落されたようでした。これが私のアイデンティティを探す(構築する)旅の始まりでした。思春期の奔流に巻き込まれていったわけです。
夏が過ぎて秋がやってくる中で、クラクラした頭で読んでいたのが、「フラニーとズーイ」でした。「ライ麦畑」は分かりやすかった。だから衝撃もあったのでしょう。実に分かりやすい小説でした。その反面、「フラニー」は、当時の私にとっては難解でした。1行読んでストップし、また1行読んでストップする。そうやって道なき道をかき分けて進んでいるような小説でした。いや、進んでいるのか後退しているのかさえも分からない。そんな方向を見失った感じがありました。
ライ麦畑と比較して、この小説はいったい何なのだ、と思いながら、読んでいたと思います。そして読後感も、パっとしません。衝撃もなければ、感動もない。ただただ憂うつな感じが広がっている。その憂うつ感に、さらに落ち込む。そんな感じでした。
いまから思うとそれは当然のこと。自分がこれまで信じてきた、子どもじみた規範がライ麦畑で揺さぶりをかけられ、ファンタジーではない、現実(大人)の時空の中にほうりこまれたわけで、これから自分のチカラでその道を作って進んでいかないといけないわけで、それは途方もない作業のように、青年の目には映るでしょう。その憂うつなのです。
フラニーとズーイは、そういう思春期の、あーでもない、こーでもない、という迷いを、これでもか、これでもか、と描いているのです。サリンジャーの神経衰弱的な書きっぷりです。自分もそこにほうりこまれ、背中をおされるようにそこを歩き、そしてフラニーの世界が追い打ちをかける。そんな状況だったのです。クラクラする。神経過敏になって憂うつになるのは当たり前ですね。今から思うと、そう思えるですが、思春期の当時はそういうことは分かりません。ただ、ただ憂うつ。ただ、ただ過敏。
この本が難解だったのは、これまでの世界観が大きく崩れ去った中で(実際はそんなに壊れてはいないのですが)、それを新しく構築しないといけない状況下だったため、破壊された破片を拾いながら歩いていたために、なかなか進まなかったからでしょう。
(このような世界観の反転はカウンセリング中でも起こる現象です。相談者の方の再生の光が見えてくる時期ですが、夜明け前の暗い時期であり、相談者、治療者ともにしんどい時期です。)
さて、フラニーとズーイですが、2014年の春、新しい翻訳が出ました。この記事も、その本を書店で見て、ああ、そういえばかつて読んだことがあったな、と懐かしい目を向けて書き始めたのです。その本とは、村上春樹によって翻訳されたフラニーとズーイです。
村上春樹はかつて「ライ麦畑」も翻訳しています。その続編ということなのでしょう。私は、以前、彼の翻訳本を読んで落胆した覚えがあります。それは、彼が翻訳した「熊を放つ」というアービングの原作を読んだときのことです。それまで、アービングの「ホテルニューハンプシャー」を読んでおり、これが素晴らしい、家族を描いた小説だったので、熊を放つも、そのようなムードを期待して手にとったのでした。しかし、「熊」を読んで、筋の間から漂ってくるムードは、アービングのそれではなく村上のムードになってしまっていると思いました。ストーリーは共感できるものなのですが、そこには彼独特のムードが漂っており、アービングの世界観ではなくなっているように感じました。それは村上の才能ではあることには間違いはないのですが、翻訳の世界ではその才能は悪い方向へ向かいます。原作が台無しになるという方向です。
この体験があるため、村上訳のフラニーとズーイを手にとることがなかなかできませんでした。村上に「普通の」思春期の感性が訳せるのか。フラニーにおいては、彼の世界観はどの程度抑制されているのか。彼はもともと抑制の効く作家なので、どれだけ自分を抑えてサリンジャーの世界を表現できたかのか、そういう視点では、この翻訳に興味がありました。実は、村上訳のライ麦畑も購入していたのですが、こちらは全く読んでいません。読んでしまうと、自分の思春期に感じていたムードが壊されてしまいかねないような、残念な結果になってしまうかもしれないという危惧があったからです。恐怖ではないですが、残念なことになってしまう。それなら、そんなことに時間をかけるよりは、別なことをしよう、という程度です。
アービングの小説には、かなり健全な普通の世界が広がっているように思います。いろいろあったけれど僕たちはこれからもやっていくね、という世界です。結局のところ人生を肯定する感覚が根底に流れています。彼はガープの世界という名作も書いています。ホテルニューハンプシャーも映画になりましたが(私の好きな女優ナスターシャ・キンスキーが出演しています)、ガープも、ジョージ・ロイヒルによって映画化されています。この監督は、明日に向かって撃て、スティングなどの監督でもあり、アメリカンニューシネマのムーブメントをけん引した作家と言えるでしょう。どちらの映画もロバートレッドフォードとポールニューマンが出ています。私にとっては10代の頃、自分の青春と重なる映画です。懐かしい時の流れ、「普通の」憂うつな思春期を生きていた頃を思い出します。
□思春期とは
さて、この記事の本題は、思春期とはどういう時期なのか、ということでした。
思春期とは、学童期から成人期へ移行する時期のことを言います。思春期自我が芽生えて学童期心性が維持できなくなる期間です。移行期ですので不安定な時期です。親(特に母親あるいは母親に変わる養育者)や学校の先生から学んだ生き方(倫理規範)にしたがって生きている時期が学童期です。それは外からもらったものなので、自分のものにしていかないといけません。倫理規範に修正をかけて、自分のものに内在化させていく過程、それが思春期です。親の生き方を自分の生き方として昇華して身に付けていく時期です。
この親の生き方の修正をはかって新しい親子関係を模索していく中で、親子葛藤(特に母子葛藤)が生じます。親の倫理規範に反抗して、自分のものにするため(身に付けるため)の反抗です。これが思春期が反抗期と言われるゆえんです。親への怒りと、親から切り離される恐怖の両極端を揺れるという葛藤の苦しみがあります。子どもが感じるこの葛藤は、親子の葛藤(親子ケンカ)として出現し、親と子は、愛着関係があるからゆえ、連動して進み、この葛藤を抜けていきます。子どもが成人になる瞬間です。
思春期の葛藤は、自分の内側にある葛藤ではありません。親からもらった、まだ内在化されていない「外側の」規範と、それに違和感を覚える自分自身の葛藤です。つまり外と内との戦いになります。自分自身の内戦ではない分、少し気は楽です。これと比較すると、成人期の葛藤は、自分の内側にあるもの同士の葛藤です。内在化されている規範Aと規範Bの戦いです。内戦なので、この戦いは壮絶を極めます。自分の内側の葛藤であるので、この葛藤と4つに組んだとき抑うつ感が表出します。これがうつ病です。思春期葛藤は内側の葛藤ではないので、うつ病にはなりません。成人期というのは成長している分、悩みも深いのです。
仮面うつ病、軽症うつ病などの「新型うつ病」は、この葛藤の視点からみると、内面化した葛藤ではないので、本当のうつ病ではありません。葛藤が内面化していれば、仕事には行けないけれど遊びには行ける、なんてことは、罪悪感のためにできません。「なんちゃってうつ病」、「うつ病もどき」と呼んだほうが適切で、成人になりきれていない思春期心性の病理の一つなのです。うつ病ではないので抗うつ薬なども効きません。
私たちはどのように思春期から成人期に至るのでしょうか。子どもの心的状況に焦点を合わせると、まず親への怒りを自覚しますが、この怒りは隠そうとします。まだ恐怖のほうが怒りより勝っている時期です。次に、怒りがいよいよ表現されだします。それにしたがって親子対立が始まります。恐怖よりも怒りのほうが大きくなる時期です。思春期の一番典型的な時期がこの時期です。最後には葛藤の両極を等しく感じ始めます。つまり怒りと恐怖を同時に感じているような感じです。統一できない矛盾を同時に感じている時期です。これが感極まると、葛藤が消滅します。弁証法でいう、正反合の「合」に当たる部分です。気づきを得る瞬間です。こうして、自我同一性(アイデンティティ)が完成し、自由と責任を獲得します。親と和解し、親とは独立した者同士の関係として、愛着関係が普遍化され、思春期が終わります。子どもが成人になる瞬間です。
例えば、親が「つらいことがあっても人に頼らずに自分だけで頑張る」という生き方をしていた場合、子どもはそれと同じ倫理規範を学童期に身に付けます。そのため、この子の思春期は激しいものになります。それはかなり厳しいルールだからです。その激しさの表現として、家庭内暴力、非行、万引き、薬物摂取、リストカット、過食嘔吐、引きこもりなどの思春期問題として、子が親につきつけてくる場合があります。(これらすべてが、この思春期問題から起因するわけではないことにもご注意ください。)子どもは思春期に、この親からもらったルールに反抗することで、自分のルール、例えば「人に甘えることがあってもいいのだ」という生き方を取得します。そして自分の生き方として、その新しい自分流の規範を内在化させることができた時、成人に至ります。ようやく思春期を抜けることができるのです。
この親の生き方(倫理規範)が厳しい場合、子どももそれを乗り越えないといけないために、反抗は厳しいものになります。そして、この子の反抗を通して、親のほうも心理的な成長を遂げます。親子で発達する時期が、子どもの思春期なのです。親が、子どもの反抗の意味を理解できない場合、つまり親の心理発達が進まない場合は、子どもの反抗は空振りと終わります。そして思春期問題は長期化します。子どもがいつまでたっても成人にならないからです。子どもが30歳頃になるまで引きずる家庭もあります。この場合、親の成長をアテにできないので、子どもは親を切り離して、自分で進んでいくしかなくなります。親が子どもの怒りを理解してくれないので、子どもの生き方も厳しいものになります。
(1) 子どもが怒りをがまんしたときは、頭痛・腹痛などの身体化症状を出して登校しなくなります。
(2) 怒りをこころ深いところに押し込めた(抑圧した)場合は、拒食症などの症状を出してきます。これは無意識的な行動ですので、本人はどうして拒食になっているかの自覚がありません。
(3) 子どもが怒りを抑圧したり、それを表出したりしながらひとりで葛藤している場合、つまり親とのやり取りが途切れている場合は、リストカットなどで怒りを表出する自分に罰を与えます。あるいは過食と嘔吐を繰り返します。子どもは親が怒りを受け止めてくれないので手ごたえがないので苦しくなります。親とケンカにならない苦しみによって、子どもは病気になります。
(4) 子どもは怒りを表現するのだけれど、親が受け止めきれない場合は、子どもの怒りは空振りとなり、不登校や引きこもりが長引きます。家庭内暴力もひどいものになり、軽症うつ病などの症状も難治性のものとなり、非行・薬物乱用・飲酒などの行動化が激しくなります。ちなみに、成人期の飲酒は、自分の中の葛藤を越えていくために、社会で生きようとするために飲むのですが、思春期の飲酒は親へ怒っているから飲むのです。この場合は、親が尻拭いをしていくべきで手放してはいけません。思春期問題の原則は、「親が世話を焼く」ということに尽きます。自立を促さないこと。親密な関係を作ることができれば、子の自立は自然と進みます。逆に自立させようとすると、思春期に不可欠な、親子間の怒りのやり取りが妨げられて、症状が悪化し遷延化していきます。このように自立を促してこじれた状態になると、境界性パーソナリティ障害として表現されます。
親の持っている生き方がマイルドな場合は、子どもも乗り越えるハードルは低くなるので反抗もマイルドになります。具体的には、親子の間で怒りのやり取りができている場合です。子の意見には賛成できないけれど、子どもがある事情で怒っていることは親のほうでも理解している場合です。こういう場合、子どもは親との会話が少なくなり親を無視しはじめ、自分の部屋で過ごす時間が増えて、親から離れていき、自分で責任を取る自立化への道を歩みだします。このように大きな問題なく解決されていくのが、普通の思春期です。
青年期(思春期)の発達課題として、自我同一性の確立ということがありますが、これはどういうことかと言うと、「自分とは何か」ということが分かった状態です。これは学童期の倫理規範が内面化した状態なのです。つまり、社会的にコナレタ状態。社会で柔軟に生きていける状態。社会的アイデンティティが確立した状態が、自我同一性の確立ということなのです。
親がきびしい生き方を選択してきた場合、子どもは思春期に大きな反乱を起こすということをお話ししました。それは親の倫理基準に対して、「その考え方はおかしいから変えなさい!」という子どもからの問題提議なのです。そうやって子どもがさまざまな事件を起こすことで、親は悩み、自分の半生を振り返り、原家族との問題が浮き上がり、自分が大変な人生を送ってきたことを自覚し、子どもが身を呈してそのことを教えてくれていることに気がつきます。親の止まっていた成長がここで一段階ステップアップします。そうなることで、子どももようやく落ち着いて自分の倫理基準をコナレタものに作り変えることが終了し、内在化が完成し、ようやく思春期も終わります。これ以降は、親との人間関係は、普遍的なものを目指すことになります。親子関係でなく、人間と人間の関係になっていくのです。
子どもが出してくる思春期問題というのは、普通は、このような親子葛藤、特に母子葛藤なのです。子の反抗は、母親自身が本来持ち続けてきた葛藤をあぶりだし、それを解決へ導くためのものであり、母親の心理発達を促進させるのです。子が思春期を通過していくことで、子も成長し、母親も成長するのです。
子どもの反抗が終えることで、子どもは親から自然と離れて行きます。これが社会的アイデンティティを獲得した子どもの自立です。しかし、親の生き方がきびしいときはなかなか子どもが親から離れることは難しいです。先にも書きましたが、この場合、自立、自立と叫んでも、効果は薄く、逆に、親と子が親密な関係に入ることが大切です。自立と言わない。そうやって子どもが安心すると、子どもは離れていきます。母親が深い葛藤を抱いて生きてきたときは、このような非典型的な発達の思春期関係に入ることがあります。このときこそ、母親と子どもが同時に、一緒に良くなっていくことが必要なのです。ボーダーラインの治療では、よく「自立」ということが言われますが、実は「自立」ではなく、真の親密な関係を作ることが必要なのです。治療では逆のことをやっているため、なかなか症状は良くなりません。
思春期の頃は、子どもは大人に対して、すべて親の幻影をそこに見ます。ですからカウンセリングに来たとしても、カウンセラーを親として見なします。そのため、自分のことはあまり話しません。カウンセラーを、反抗している親と同類のものとして見なしているからです。これは特別な心性でなく、思春期としてはいたって普通の心性です。このため思春期のカウンセリングというものは成立しないのですが、それでも「親に連れて来られた」という気持ちを理解し受容していくことで、カウンセラーにこころを開き出す可能性はあります。それには、子どもが来談しているのは、自分を治すためというよりは、母親の生き方を修正させようとする子の想いがこもっていることを理解することです。こういう心理的な背景があるため、思春期カウンセリングでは、子どものカウンセリングよりも母親のカウンセリングのほうが重要であるのです。
母親は成人期までは成長してきたが、思春期の家族問題をひきずっているため、こころの苦しみがそこに渦巻いて、葛藤を抱えたままの状態で立ち尽くしています。このこころの壁を前にして、子どもの反乱が起こっているのです。母親が自分の緊張に気がついて、その緊張を解くことによって、子どもも自分の緊張を緩めることができるのです。子どもが親の心理発達を促すのです。子どもの反乱が、母親を助けるのです。
どうして子どもが学校へ行かないのか。どうして子どもが摂食障害になっているのか。どうして暴力をふるうのか。それを母親が、自分の苦しかった半生を重ね合わせながら理解できたら、自らの原家族との葛藤を理解できたら、子どものそのような行動も理解できます。それによって子どもの症状は消失します。
母親自身の、気がつかなかったガマンや怒りや恐れを話すことです。子どもへ優しくできない気持ち、自分が小さいときからしてきたガマン、そして配偶者に対して抑えてきた気持ちを話すことです。まずご自身が抱えてきた葛藤を十分に話すことです。警察へ連絡したり、その場から立ち去ったり、子どもだけを病院や相談室で治療しようとしないでください。まず母親が受け止める。それを一人でやるのはたいへん苦しい。自分の原家族との葛藤の直面もあるので相当苦しい。そのために、母親自身が相談室に訪れる。子どもでなく、母親が相談にくる。そして子どもの葛藤(気持ち)の理解を深め、どうやって子どもと交流していけばいいのかをカウンセラーと一緒に探していく。自分の怒りは原家族の中では扱ってもらっていないので、どのように子どもに接していったらいいのか、母親は分かりません。それをカウンセラーと一緒に探していくのです。これが本来の思春期問題の解決方法です。
□思春期を通過しない人々
話は少し変わりますが、親から虐待を受けて育った子どもは、親との愛着が切れているため母子葛藤という形は存在せず、定型的な思春期を生きることはできなくなります。ファンタジーとしての親への愛着はありますが、それは所詮、幻なので、本来のしっかりした愛着とはほど遠いものです。そのため今回の話とはまったく別な生き方をすることになります。むしろ、被虐者は、思春期を通過せずに、成人になってしまっています。
これはどういう状態かというと、一般的には思春期を通過することで社会的な自己が形成され成人になります。けれど被虐者は、思春期を通過できないので、社会的自己を形成できません。これでは大人社会でやっていけません。そのために学校の先生や友達や世界文学全集などからある程度の生きる様(さま)=世間知(せけんち)というものを学びます。それを鎧として生きていくのです。これはとても大変なことです。こころは幼児のままなのに意識して大人をやらないといけない。幼児が重たい鎧を着て生きている、それを想像していただければ、被虐児が思春期を通過せずに成人として生活していく大変さを、ほんの少しですが、理解いただけるかと思います。普通に思春期を通過した人、つまり親との愛着形成ができた人々は、何の疑いもなく自分の感性にしたがって社会的自己を自由に表現しながら社会を渡っていけるのです。
被虐者は、愛着がないので、10代の頃、親に反抗することもできません。憎むことは愛することの裏返しなので、愛着がないと憎むこともできないのです。これはかなり特別な生き方です。こころの発達としては非定型なものになります。
例えば、被虐者が摂食障害になった場合、過食するが吐かない、やせている自分の体がみっともないと思うので隠す、拒食や過食をするときに母親への葛藤がないなど、典型的ではない摂食障害の行動様式を見せることがあります。本来の「正統的な」思春期の摂食障害は、過食したら吐く、拒食して骨だけになった自分は美しいので堂々と他人へ見せる、表面化していない母への恨みつらみがあるなど、典型的な行動になります。また、強迫的な症状は、子どもにはありがちですが、それが大人になっても続いている場合、虐待を受けて育った可能性もあります。しかし、強迫症状は、統合失調症や強迫性パーソナリティ障害、発達障害にもみられる行動なので、正しい鑑別が必要とされるところです。20代前半くらいまでは、統合失調症や強迫性パーソナリティ障害などの診断をつけられないので、確定診断をせずに治療が進むこともあります。
被虐者の治療が進み回復してくると、彼らは思春期をジャンプして一気に壮年期あたりへ発達を遂げます。これは目を見張るばかりの成長で、この心理発達も定型とは言えません。非常に不思議な、特殊な発達を遂げるのです。治療していていると、彼らの回復には驚かされることが多いです。ここが被虐者の心理発達は非定型と言われるゆえんなのです。思春期は通過しないが、一気に壮年期へワープする。ここに被虐者の希望があるわけです。
子どもが借金やギャンブル問題で金をよこせと暴れて、家庭内暴力がひどいために親が相談に登場するケースを考えましょう。思春期問題をかかえて、倫理規範の内在化のために暴れている場合、親が金を与えても暴力は治まることはありません。なぜならお金が問題なのではなく、親の生き方が問題だからです。暴れるとやすやすとお金を与えるという、その親の生き方への反抗だからです。親がそのことに気づかない限り暴力は治まりません。また、お金を与えると暴力が治まりニコニコしだすような場合は、その子どもは思春期問題を抱えているというよりも、発達の問題があるのかもしれません。依存症からの回復プログラム、嗜癖プログラムに通わせても、ほとんど効果はないでしょう。
このように思春期問題のように見えながら、実はそうではないというケースもあるのです。病院でも思春期専門を看板に挙げているところもありますが、正しく見立てて診療できているかは怪しいところもあるのではないかと思います。(私自身への自戒も込めて。)そのへんが思春期臨床は難しいのです。
発達障害を持った人々も、心理学的には思春期に入れません。学童期でストップします。自閉症スペクトラムは人間理解の異質性、軽度知的障害、ADHD、LDは人間理解の幼稚性によって適切な社会性を作ることができないために学童期を脱出することが困難なのです。
また、愛着はあるのだけれど精神年齢が子どものままの人も、学童期で発達が止まっています。精神医学的には、自己愛パーソナリティ障害(誇大型)、強迫性パーソナリティ障害(肛門期人格)などの診断がつくこともあります。弁護士や医者や教員など、知能が高く専門性の高い職業の方々にも時々見受けられます。自己愛性パーソナリティ障害の診断がついている人で、実は、発達障害(軽度知的障害)だったという人もいます。
統合失調症スペクトラムの人々は、いったんは思春期までは発達するのですが、もともと遺伝的に持っていた脳機能の障害が何かのライフイベントをきっかけに発症して、思春期を通過できずに学童期へ退行します。何かのライフイベントとは、自分の社会的アイデンティティ形成に関する失敗に関係することです。思春期までは、なんとか一般の人のようになろうとして自己を築きあげようとするのですが、それが脳機能的にできなくなる、その不全感によって発症します。統合失調症の方々は、一般的には、思春期までは到達して、そこで自己の社会的アイデンティティ形成の局面に直面したときに発症するので、発達障害や自己愛の方々とは違って、大人に近い心理的な体験を経験している強みがあります。そのため治療による効果もそれらの方々に比べると良いものになるように思います。クスリは飲み続けることになるかもしれませんが予後は良いのです。
精神科医で僧侶でもある広沢正孝氏の「こころの構造からみた精神疾患」には、一般的なこころの構造を追い求めるゆえに、普通の人になろうとするゆえに発症していく事例を多数みることができます。彼は、ユングや西欧が求めた、中心に自己を置いた、放射状の自己形成=胎蔵界マンダラでなく、自閉圏と親和性の高い格子状の自己形成=金剛界マンダラが示す生き方の選択を勧めています。現在の世の中は自己を中心とした成長、これが一般的な定型の精神発達なのですが、それを求めすぎます。それによって生きづらくなって発症する一つの病が統合失調症なのです。日本に限らず、成長を目指す21世紀社会は、ますます胎蔵界マンダラ化しています。弱者には生きづらくなっているのです。胎蔵界マンダラと金剛界マンダラについては、記事を別にして書こうと思います。
発達障害、自己愛パーソナリティ障害、統合失調症スペクトラムの方々は、普通の価値観では生きられない人々です。ですから、ご自身の価値を、一般的な発達を遂げる人々とは別なところで見出して、自分を取り戻しながら生きていくことが治療方針になります。ある意味、世の中とは別の価値観を示す人々としてその存在感は、21世紀においてますますと重要になってくるでしょう。
余談になりますが、誤診で多いのは、被虐者なのに発達障害の多動・自閉と誤診してしまうケース、解離性障害(被虐)、発達障害、器質性精神病なのに統合失調症の幻聴・幻覚と誤診してしまうケースなどです。(躁うつ病の幻覚などは統合失調症の幻覚発症と類似しています。)相談者の方から、発達障害や統合失調症などの病名を告げられた場合は、治療者はいったんそれらを保留にして見立てを立て直すことが必要でしょう。治療によって対人関係や社会適応が良くなるのは、解離性障害(被虐)>統合失調症>発達障害の順番とも言います。解離性障害はカウンセリングで完治し、統合失調症も薬でかなりの部分が改善されます。長期に渡る服薬でも改善しない統合失調症は誤診の可能性もあり、虐待のケースか発達障害を疑ったほうがいいかもしれません。
□ある少女の訴え、ゾマーさんのこと。
思春期とは、親から受け継いだ規範を自分の中に取り込む、つまり内在化する時期でした。それは心臓移植に匹敵するくらいもの。こころの移植です。違う心臓を自分の体内に移植するときには、異物が体内へ入ってくるわけなので、必ず激しい免疫反応が出ます。この拒否反応が思春期の抵抗として表現されるのでした。こころの移植とは、タマシイの移植でもあり、思春期の時期に、普通の人々はタマシイの問題にも直面することになります。様々な神秘体験を経験する人もいますが、これらは神秘という側面よりも、もっと身体的な側面、自己免疫反応のひとつとしても捉えることもできるでしょう。ここには思春期と身体化の抜き差しならない関係があるのですが、その話はまた別の機会に譲ります。
統合失調症は、身体的にみると、脳の体積が何らかの理由で萎縮し、それを修復しようとして脳に炎症が起きるときに発症します。心因ではなく脳の障害です。急性期の幻覚・幻聴、妄想はこの炎症のために起きてくるのです。脳の体積が減るわけなので、急性期を薬でなんとかしのいでも、体積が元に戻るわけではありません。慢性期の陰性症状は非常に長い期間残ります。患者の方がそれと上手に付き合っていけるようになると統合失調症の治療はひとまずの終わりとなります。
それとは別に、非定型精神病や発達障害の幻覚や被害妄想、思春期の氾濫、解離性障害などは、身体的にみると、ストレスによる自己免疫疾患です。こちらは心因になります。過剰な免疫反応としての炎症が脳に起きるのです。この急激な炎症により、幻覚・幻聴が出現しますが、炎症が収まれば、脳の萎縮はないので予後が非常に良いです。統合失調症のような陰性症状はありません。どちらも幻覚が出現することがありますが、このように発生の原理が全く違うのです。
このような差はありますが、幻聴や妄想は、広くみると炎症作用によるものです。思春期のタマシイの取り込み作業をみていくとき、情緒が不安定になるとき、この「炎症を起こしているんだな」という視点は役に立つことがあると思います。「こころの炎症、タマシイの炎症」という視点です。
ある相談者のかたから本を紹介いただきました。ゾマーさんのこと。ドイツ人で、「香水」という小説で有名な作家の短編ファンタジーです。1人の少年が学童期から思春期へ入る時期の話です。その少年の日常の中に、ゾマーさんが遠景として置かれます。ゾマーさんは壮年期の男性です。妻と二人暮らしで、何も話すこともなく、日が昇って日が沈むまで、毎日毎日、ただひたすら歩いています。歩くことが彼の仕事のようです。
少年の日常はゾマーさんと交差することなく過ぎていくのですが、ある日、ヒョウが激しく降ったとき、少年と父親は車で待機しているところで、ヒョウの中を歩いているゾマーさんに遭遇します。父親は車の中へ入ることを促すのですが、ゾマーさんは「ほっといてもらいましょう」と拒否してヒョウの降る中へ消えていきます。この出来事が唯一、少年とゾマーさんが接点をもった出来事でした。
少年は青年になり、ある夕暮れ、自転車をこいで家へ向かっている途中にゾマーさんを見つけます。ゾマーさんは道から外れて、広い湖の中へ入って行きます。それでも歩くことを止めません。そしてずんずんと進み、湖の中へ消えていきました。少年はそのまま誰にも知らせずに帰宅します。ゾマーさんが消えたことについては少年だけが知っているのです。物語はここで終わります。
ラストはゾマーさんが自殺をするわけですが、何らかの心理的葛藤が描かれているわけでありません。ただ仕事のように前へ進む。葛藤の入る余地などないかのように。そのようなものさえも横に置いてしまう圧倒感を、この水の中へ分け入っていく場面に感じます。ゾマーさんは、この少年にとっての何かの比喩ではあるのですが、普通に考えると、思春期を通過していくときの少年の学童期心性の死と読み取ることができるでしょう。学童期の規範が死んで新しい成人規範を迎える、つまり思春期のこころの成長を表現したファンタジーとしての読み方です。そして、ゾマーさん本人は、この少年の思春期衝動そのものであるとも捉えることができます。
しかし、それとは別に、このゾマーさんという人の実直さを感じずにはいられません。目的があるのだか、ないのだか、そういうことは問題でなく、ただ歩く。このひたすらな行動が、彼が生きのびるためには必要なのでしょう。止まらずにどんどん前へ進んでいったものだから、湖へと外れた彼の道程によって彼は死んでしまった。これは自殺と呼ぶにはあまりに実直すぎる行動です。ただ歩くとい行為の延長線上に死があった。死というものはそれだけに過ぎない。
この実直さは、統合失調症の方々がもつ硬直性にも似ているように思いますが、それだけではない。統合失調症の方々は途中までは普通に心理発達をしている、つまり思春期経験はあります。そこは発達障害の人々と比べると、思春期を体験しているという点で、希望がありますし、死ということについて、彼らなりの考えがあります。このゾマーさんは、そのような希望的な、あるいは絶望的な側面からは切り取れない感覚を覚えます。これは何か。思春期を通過する、一般的な心理発達を遂げた人々には分かりずらい側面です。
ゾマーさんは少年のこころを表現したものですが、思春期心性だけではない、このゾマーさんとはいったい何者なのか。
かつて相談室へ通ってきた少女がいました。彼女は律儀にも曜日を決めて、定期的にリストカットしており病院で鉄剤を処方されていました。その治療の効果(血液中のヘモグロビン濃度の上昇)が表れてきたとき、「貧血が治ってきちゃったよ。どうしよう、何もなくなる。」と、唸ります。思春期とは、何かであろうとする時期。そういう自己を模索する時期。その時期において、貧血というアイデンティティから引き剥がされた彼女は、「私はもう何にもなれない。」と訴えます。
この訴えには炎症のようなヒリヒリしたものを覚えます。治療をすることでこころが炎症を起こす。良くなっていくことで消されていくものがある。それは成長による純粋性の喪失というものとは、ちょっと違う。つまり思春期の感傷とは違うもの。
谷川俊太郎が「かなしみ」で詠んだ、
あの青い空の
波の音が聞こえるあたりに
何かとんでもないおとし物を
僕はしてきてしまったらしい
良い詩です。この喪失感は思春期そのものですが、このような純粋性とは違う。宮崎駿の風立ちぬで描かれている喪失も、この種の喪失でしょう。多くの人は思春期を通過して成長するからこそ、この喪失感に共感し大ヒットしたのです。
むしろ富永太郎の「影絵」の、
半欠けの日本の月の下を、
一寸法師の夫婦が急ぐ。二人ながらに 思いつめたる前かがみ、
さても毒々しい二つの鼻のシルエット。
(中略)
半欠けの月は、今宵、柳との
逢引の時刻ときを忘れてゐる。
この詩の、得たいのしれない不安。半月?一寸法師の夫婦?急ぐ?鼻のシルエット?この息をひそめたような不安によってこころが炎症を起こす。この炎症の炎の中に、一生懸命にリストカットして生きようとする少女の生き方というものが見え隠れしているのです。なぜ炎症を起こすのか。生きようとするから、治ろうとするから炎症を起こすのです。
得たいのしれない不安とは、統合失調症の急性期が発症する前の、おどろおどろしい前駆症状に近い雰囲気ですが、それとも違う。明らかな線引きがある。ゾマーさんが統合失調症ではないのと同じようなものです。この炎症には実存的な「タマシイ問題」がからんでくるのです。
タマシイ問題は死に限りなく近いところにあります。自殺の原因で最も多い疾患はうつ病ではありません。統合失調症です。タマシイ問題は、統合失調症とは一線が引かれているので、タマシイ問題によって実際に命を落とすかは分かりません。そこには第三者が関与できない微妙なこころの力学が働いているからです。しかしそれでも、一番、死に近いのは、実は統合失調症ではなく、タマシイ問題なのです。それがゾマーさん。人があっけなく命を落とすときは、このタマシイ問題が介在しているように思います。
この「私はもう何にもなれない。」と訴える少女にとってリストカットとは、「ゾマーさん」そのものであったのでしょう。
□フラニーとズーイ、ふたたび
村上春樹訳のフラニーとズーイへ戻ります。文庫には彼が書き下ろした小冊子が入っていて、「こんなに面白い話だったんだ!」というタイトルが踊っています。村上的に言うならば、このような表題がついた小説で面白い小説に出会ったことはありません。あぁ、やっぱりという感じがしました。実際読んでみて、村上臭はさほどありませんでした。村上臭を出せる余裕がなかったのかもしれません。それくらい饒舌なサリンジャーが居て、原文が練り上げられていたのでしょうか。村上を意識せずに読めました。その点はよかった。取り越し苦労でした。ただ、面白い小説だったかというと、それほどでもないな、という印象です。たぶん、小劇場の演劇などが好きな方は、設定として面白く読めるのかもしれない。
話の筋は、前半はフラニーの話。彼氏とデート中にフラニーが神経衰弱に陥っていく話。フラニーは東洋の宗教の神秘主義に傾倒しています。これは心理学的にみると、普通の思春期の妄想やら葛藤やらの話です。外側のものを内側へ取り込むときに起きる摩擦=思春期です。自分で自分を罠に落としこめて行く話しです。螺旋階段を下るように、どんどんと下降していきます。まるで自家中毒にかかったように。場面は高級レストランのカウンターです。
東洋の宗教の神秘主義とは、1950年代から沸き起こっていたアメリカでの禅のブームなどを指します。この神秘主義は1980年代にニューエイジというムーブメントとなって西海岸を中心に盛り上がります。ベイトソンなど知の巨匠といわれる人々がこぞって神秘主義へ傾倒します。ズーイはこの潮流に、1950年代にして、果敢に反旗をひるがえしているのです。
後半のズーイでは、フラニーの兄であるズーイとフラニーの会話が充満しています。登場人物は、彼らの母とフラニーとズーイ、この3人。場面は、ニューヨークシティにある彼らの実家です。最初は浴室に入っているズーイとカーテン越しの母親との会話。次が場所をフラニーの部屋に移してのズーイとフラニーの会話。これだけです。神経が過敏になっている(ボーダーライン的な)フラニーを宗教の神秘主義の薄っぺらな泥沼から救い出そうとするズーイの物語、表面上はそのような話です。
ですが、これは心理学的に読むと思春期の物語なのです。
実家では壁のペンキの塗り替えが進行中です。これはフラニーの心的現象の暗喩のように読めます。フラニーのこころの中が塗り替えられている途中であるということを示しています。つまり外側の倫理規範を自分のものにしている途中であるということ。それは思春期そのもので、そのために神経衰弱になっている、不安定になっているのです。
物語の最後でズーイがフラニーに電話から話をするシーンがあります。そこに、「おまえは太ったおばさんのために靴を磨くんだよ」という表現が出てきます。この靴を磨く作業は、思春期を通過していく時期のことを表わしています。倫理規範を内面化していく作業のことです。
そして「太ったおばさんじゃない人間なんて、誰ひとりいないんだよ。」と続く。みんな太ったおばさんになる、ということで、これは子どもから「成人」になるというふうに読み取れます。つまり倫理規範が内在化された状態、大人になった状態です。
「その太ったおばさんというのが実は誰なのか、君にはまだわからないのか?ああ、なんていうことだ、まったく。それはキリストその人なんだよ。」この最後の言葉でフラニーは覚醒します。キリストとは、倫理規範が内在化された状態で、成人になったという比喩です。フラニーもここでようやく子どもから大人へ成長したのです。東洋神秘主義の服を自由に脱げるようになったのです。服は自由に着たり脱いだりできる。着てもいいし脱いでもいい。これが大人です。
フラニーとズーイは、思春期の子どもが成人になる瞬間を切り取った小説とも言えるでしょう。
最後の電話のシーンの直前に、ズーイがフラニーの5階にある部屋から下を眺めるシーンがあります。このシーンが、おそらく村上春樹はハイライトだと思ったのでしょう。文庫の帯の裏側に、わざわざその会話を掲載しているからです。
「まったくなあ」とズーイは言った。「世の中には素敵なことがちゃんとあるんだ。紛れもなく素敵なことがね。なのに僕らはみんな愚かにも、どんどん脇道に逸れていく。そしていつもいつもいつも、まわりで起こるすべてのものごとを僕らのくだらないちっぽけなエゴに引き寄せちまうんだ」
これはズーイが窓の下で、小さな女の子とその飼い犬が繰り広げているかくれんぼに目を奪われたときの感想です。彼は女の子と犬が楽しげに5番街とセントラルパークの方へ向かって歩いていく姿をずっと追いかけます。そのときにつぶやいた言葉です。
ライ麦畑でつかまえてでも、最後のほうで、主人公のホールデンがつぶやきます。「僕は子どもたちが崖から落っこちないように、ここにいて、子どもたちが走ってきたら捕まえて、草原のほうに返してあげる役目があるのだ。」このズーイのつぶやきは、このホールデンのつぶやきを思い起こさせます。
村上春樹の著作にも似たような表現はたくさん出てきます。処女作の風の歌を聴けでは、病気で動けなくなった人がベッドから窓の外の風景を見ていて、風にひるがえる葉っぱの裏側に真実が詰まっているのを見つけるシーン。ねじまき鳥クロニクルでは、アヒルのヒトタチは山奥で冬になると凍った氷の上を足をすべらかせながら歩いているのだろう、と回想(想像?)するシーン。
このような日常の中のほんの1シーンに真実は隠されているのですが、カウンセリングも全く同じで、日常の話をする中で相談者の方々は回復していくのです。日常を話して整理していく。この作業こそが、普遍的な気づきを得ていくのに必要なことなのです。相談室の中で何か魔術的なことが繰り広げられているわけではないのです。魔術的なものを施術するということは、フラニーを宗教的な神経衰弱に陥らせていったことと同じことをすることで、回復とは真逆なことなのです。
余談になりますが、思春期の小説は誰にでも書けるわけではない、サリンジャーは、その才能のある数少ない作家のひとりである、と誰かが言っていました。村上当人だったかもしれませんが、どこで読んだのかさっぱり忘れているので断定はできません。
さて、村上春樹が思春期の小説を書けるかということになると、非常に答えるのが難しい。思春期を持たなかった人の話は、彼の独壇場でしょう。しかし、普通の思春期を持った人の話は書けるのか?思春期を持たなかった人というのは、思春期が軽かった人とは全く違う次元の話しです。軽かったという人は思春期を通過していますが、持たなかったという人は通過していないのです。その差はものすごく大きいのです。
思春期を通過しているというのは、こころの発達の面から眺めると、定型発達と言えます。思春期を通過せずに大人になっているというのは、非定型発達と言えます。この非定型発達とは、発達障害とは違います。発達障害は生まれつきの脳の不具合による「障害」です。その障害によって発達が学童期あたりで止まった状態です。非定型発達とは、障害ではありません。では統合失調症はどうなのでしょう。統合失調症は、あからじめそのような素因があり、こころが発達している途中(10代後半~20代前半)で発生した脳の障害です。先に説明したように、脳の体積の減少と、それを食い止めるために脳神経細胞に生じる炎症による障害です。20歳前後の発症ということは、統合失調症の方は発達障害の方よりも、こころの発達は進んでいるのです。ですから高い学歴の方もいらっしゃいます。けれど発症と同時にその道から外れ、学童期レベルに落ちる。統合失調症は治ることはありませんが、薬で抑えていれば予後がいいのは、発達障害の人よりも適応力があるのは、こころの発達が一度は、思春期レベルを経験しているためです。
村上は彼しか書けない世界感を書いていればいいのでしょう。彼は、3作目、羊をめぐる冒険を書いたあと職業作家の道を歩み始めます。同時にマラソンを開始します。あるとき、走ることで大切なものが枯渇しないかと問われたとき、走るくらいで枯れてしまう闇程度のものだったら作家をやってはいけない、というようなことを言っています。彼はその言葉通りのことを守っていけばいい。色気を出して、通常の男女のことや通常の思春期のことなどは目もくれぬことです。彼が、そういう普通の思春期のことを書いても、全然面白くない。彼の訳したフラニーとズーイから村上臭が抜けているように感じたのは、あながち私の鈍感なせいばかりではないかもしれません。
□補遺
ライ麦畑でつかまえて、と非常に似た小説として、庄司薫の「赤頭巾ちゃん気をつけて」という芥川賞小説があります。1969年の話です。読んでみると分かりますが、本当によく似ていると思います。この小説が受け入れられたのは、時代がそのような気分だったからでしょう。ちょうど大学紛争の頃で、東大入試が中止された年です。
いまの人だったら驚くかもしれませんが、東大入試がなかった年があるのです。そのくらい世の中が激動していたのです。それが1969年です。そういう時代の熱が庄司の小説を全面に押し出したのでしょう。そのあと、彼はよく似たタイトルの小説を数編書いて、バクの飼い主をめざしてというエッセイを書き、世界的なピアニスト、中村紘子と結婚します。
時代の熱が冷めていき、彼も小説から遠ざかり、噂によると、投機の才能があるらしく、中村紘子に生活費を頼ることもなく、投機によって稼いでいるようです。本当にバクの飼い主になってしまいました。なんか、春の夢のような話です。庄司薫が思春期を通過したのかどうかはどうでしょうか。子どもでは飼い主(親)になれないでしょうから。そうすると、彼も案外と村上春樹と同じような場所にいる人なのかもしれません。サリンジャーも作家をやっていた時期は非常に短かかったです。この三人の思春期はいかに?
□番外編1:思春期のタマシイ的側面
街の木々も緑で、
空も五月晴れ、
日陰の風は涼しい。
三拍子そろっているのに、気分が冴えない日、焦りを感じる日というのはあります。身体的に別におかしくはなく、ストレスもさほど感じていない。つまり、身体因や心因でもない。そうすると原因不明の内因ということになります。
内因といえば、統合失調症や躁うつ病ということが思いうかびますが、おどろおどろしいことを感じたり、ハイテンションになったりしているわけでもなく、病的なことが起ころうとしているわけでもなさそう。
これは、おそらくタマシイの流れに乗りそこなったこともありそうです。
何なんだ?それは!?と思う方もいらっしゃるかもしれませんが、なんかそういう日もあるみたいですよ。こういうときは、どうしようもないのですが、そのうちこのことについて書いてみようと思います。
思春期の暴走も、ときどきタマシイ問題が顔をのぞかせるときがあります。そのへんは岩宮恵子さんの著作をご覧ください。
□番外編2:依存症と思春期モード
最近、日本国内ばかりではなく、世界中で退行ムードが漂っています。退行とは子ども返りです。政治の現場では、成人から思春期へ戻ったような言動がめだちます。市井の人から政治家まで子ども返りが激しい。私と同世代のこの国の首相も子ども返りをしている。なにやら思春期の葛藤が再燃しているようです。
成人期の大人が依存症にハマるときは、きまって背景には、ストレスによる思春期の再燃があります。つまり依存症の人は、まだ大人になりきれていないという側面をもっています。そういう目で見ていくと、地球人というものは、まだ成熟過程の途上にある生き物とみることもできるかもしれません。
そして地球という生き物が21世紀になって依存症を発症してしまった。だから歴史は繰り返してしまうのでしょう。21世紀に入ってしばらくたったのに、また20世紀までと同じことをしている。
地球人というものは、葛藤は消えない動物ですが、葛藤はバージョンアップさせてほしい、それが大人というものでしょう。それが進歩というものです。葛藤のバージョンアップについては、メンタルの治療を終えた人には、どういうことか分かってもらえると思います。
今後、この世界は、重篤なメンタルの患いから復帰してきた人々が一役担っていくのかもしれません。しかし、そういう人は、「担う」そういうことには興味はないことが多いですね。世界を担うということは、それほど重要ではないということに気がつくからです。人間の価値基準が自分の内面深い場所に置かれるからです。