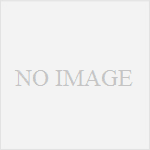小学校低学年で、まず問題になるのが、キレる子です。
学級崩壊にも登場してくる「キレる子」。どうしてキレるのか。原因として次の3つのことが指摘されています。
(1) 解離によるもの
(2) 発達障害(ADHDやアスペルガー障害)によるもの
(3) 通常の発達上のつまずきによるもの
順番を追ってみていきます。
□ 原因
(1)解離によってキレる子ども
解離とは自分を保てなくなることを言います。具体的には親や教師が叱っているときに、子どもの目が泳いでいたり、ボーっとした表情で話を聞いていない状態です。子どもは、無意識的に解離を使うことで、自分にとって危険な場所から自分を逃避させているのです。
普段、私たちは、自分というものを意識していません。意識していないときは調子よく生きていられます。そこへ何らかのストレスがかかり、自分の中に違和感が芽生えたりします。自分が何ものかにおびやかされている状況です。このとき初めて、「自分」というものを意識します。こころが静かな状態なら感じなかった違和感は、自分とは親和性がないので、この異物を出したいな、と思い始めます。そして、自分が逃げるか闘うか、無視するか、適切な行動をとることができると、違和感は減少していきます。そんなに苦にならなくなります。
しかし、精神的に何らかの損傷を受けている人々は、こころをその状態に保つことが難しく、違和感が急速に増大し、何らかの衝動(他者)によって頭の中がいっぱいになってしまいます。例えば依存症における薬物、食べ物、買い物、盗み、アルコール、病院から処方された薬などを際限なく貪(むさぼ)り尽くしたいという衝動や、怒りを爆発させたいという気持ちを抑えることができなくなります。頭が衝動に支配されてしまった状態とは、「自分」が居なくなった状態です。自分という意識が自分の身体から離れる状態です。これが解離です。自分が居なくなっているわけですので、コントロールを失って怒りを爆発させた場合、そのエネルギーが途切れるまで怒りの暴走は続きます。
人間にとって精神的な損傷とは、虐待、心的外傷(PTSD)、親や先生から良い子を期待され続けることなどです。これは子どもばかりでありません。大人になってもその傷に呪われ続ける大人は大勢いるのです。
虐待とは、身体的、精神的、性的に暴力を受けたり、親からの養育放棄(ネグレクト)などです。
親から虐待を受けた子どもは、自分を否定されるような刺激にすごく敏感です。教師からのささいな注意にも過剰に反応して、親から受けている虐待の記憶がフラッシュバックします。顔つきが変わり暴力をふるったり屋上から飛び降りようとします。ただこのときは解離しているので自分が何をやっているのかわからず、本人の記憶もあいまいです。学級が混乱するので教師は常識的な注意を繰り返すわけですが、本人には自分の全人格が否定されたように聞え、この注意がものすごく恐怖と感じられ、さらに解離します。こうなると何も感じることができず、人の痛みもわかりません。教師はこのことを保護者に連絡します。すると保護者は子どもを叱りとばし、両親にも自分の恐怖は受け取ってもらえないのだと思うと、自分を否定する刺激に対してフラッシュバックするようになり、問題はどんどんと悪化とたどります。
子ども間のいじめや教師による体罰が心的外傷(PTSD)となる場合も少なくありません。学校現場ではLD(学習障害)気味の子どもに対して、他の子どもと同じようにできないために体罰による指導という、教師からのいじめに合う子どもも多いのです。この場合も、自分を否定される場面がフラッシュバックします。教師は、あるときはこの子を受け入れ、あるときはこの子を叱ります。このような対応の混乱によって、子どもも混乱を起こしてパニックになります。そして不安がますます大きくなり、問題は悪化していきます。
よい子を期待され続けるとは、例えば、弟や妹ができてお母さんがかかりきりになってしまって甘えられない状況のとき、自分はしっかりと兄、姉として家族を支えていかないといけないのだ、甘えてはいけないし、心細い気持ちも感じてはいけない、親の言うことをしっかりと聞いて、親を苦しませることがあってはいけないのだ、と自分のこころに命じて、よい子を演じなければならないような家庭環境のことを言います。
このような子どもは、学校現場では、友達とのささいなトラブルからキレて、顔つきが変わり、怒りが納まらず、赤ちゃん返り(退行)して、わがままで我慢できない状態になり、かんしゃくを起こす「悪い子」になりがちです。しかし家に帰ると落ち着いた「よい子」であるという2面性があります。まるで二重人格のように学校と家の顔が替わるのです。担任が学校でのトラブルを親に伝えても家ではよい子なので、親は担任に悪い印象を持ち、担任との関係が悪くなるので、それは担任と子どもとの関係にも波及します。子どもは担任から叱責を継続的に受けることになり、怒りの爆発はエスカレートし、この「よい子」と「悪い子」の2面性はどんどんと強化され、悪化していきます。
(2) 発達障害(ADHDやアスペルガー障害)によってキレる子ども(この可能性はかなり低いです。)
学校でじっとしていることができず、家でも言うことをきかずかんしゃくを起こす子どもの場合、発達障害の傾向を合わせもっている可能性もあるかもしれません。しかし、気をつけてほしいのは、なんでもかんでも発達障害で片付けないようにしてください、ということです。発達障害である可能性はかなり低いのです。それを頭に入れてからここをお読みください。
ADHDの子どもの場合、多動・衝動性による育てにくさはあります。他の児童のものをとり上げたり、授業中席を立って隣の教室を見に行ったり落ち着きがありませんが、自分の好きなことだけは集中できるので、担任は、ただの怠けだと思って厳しく接しがちになります。親も、かんしゃくを起こして子どもが騒ぐため、イライラしながら体罰を含めて厳しくしつけをします。しかし、ADHDは発達の障害ではなく、脳の発達の「遅延」なので10歳前後になったら落ち着いてきます。そういう長い目で見てあげることも親子関係を築くうえでは大切なことです。
子どもは、親からも担任からも厳しい指導をされるため、わかってくれないという気持ちが強くなり、乱暴な態度が増えます。それに対抗するように親も担任もますます強く叱るというサイクルに入ります。学校の友達も、この子の暴力を怖れてこの子を排除(無視)するため、ますます孤独感が増して、押さえつけられている感じを跳ねつけるように暴力が激しくなっていきます。
またDVによって夫婦間がすさんでいる家庭の場合、体罰という虐待やDVの目撃というトラウマを発生させる環境下で、子どもは自分の精神を守るために解離を使い、その環境に耐えていきます。(このようなケースは多数あると思います。そしてこのようなケースは明らかに発達障害ではありません。)そうやって子どもはなんとか現状からの生きのびをはかるわけですが、これらの状況下では、自分は受容されていないのだ、自分は悪い子どもなんだと思いもうっ積し、自分の中にいらだちが蓄積していきます。それらは学校などで、自分の感情を刺激するほんのささいなきっかけで、他の児童への攻撃という形で爆発します。亀裂が入って暴発するわけです。担任はそれを叱りますので、不安、いらだち、嫉妬などが蓄積するサイクルへ入ります。問題はいっこうに解決していきません。
保護者からも学校へ苦情が入ります。担任は頭をかかえて不安は増える一方です。それが子どもへのさらなる叱責へつながります。子どもは自己評価が低くなり、どうせ自分なんか誰からも認めてもらえないのだという思いに乗っ取られ、多動や衝動が増加していきます。親も子どもをどうすることもできない自分に対して自信喪失となります。そして叱責してしまうことを繰り返します。問題はいっこうに改善していきません。
アスペルガー障害という器質性の発達障害もADHDと同様に、自分はどうして他人と同じことをすることができないのかという否定的な自己評価に圧倒され、担任も同じことができない子どもに対して否定的な視線を送りますので、問題のサイクルは改善していきません。(この問題は、発達障害によるものではなく、自己肯定感の低下によるものです。)
そして見忘れがちなこととして、私たちは「発達障害」という診断が医師からされると、「あの子はADHDだから仕方ない」と無力感を感じてしまうことが往々にしてあるということです。
発達障害だからキレるわけではありません。ここが大切です。もう一度言います。キレるのは発達障害であるからではないのです。それよりも虐待やDV目撃などのトラウマによる原因のほうが大きいことを忘れないようにしておきましょう。くれぐれも発達障害というレッテルによって、親御さんや先生方の思考回路が停止しないように、創造的にキレる問題を考えていくことが大切です。援助できることは現実的にはたくさんあるのです。
小学校というところは、勉強をさせるところだと思っている教師が多いので、点数で子どもを見るようになって、他人と比較しがちになります。学校というところは人間関係を学ぶところであるという視点になかなか立てないのが現状でしょう。ゆとり教育の現場でさえそうでした。これから制度が改革されて教科書が分厚くなり、学力重視の施策が教育現場へなだれ込もうとしています(この記事は2010年春に書いています。)。先生も不安です。(当然子どもも不安です。)この状況下で、発達障害傾向のある子どもがさらなるストレスにさらされる可能性はよく考えなければなりません。
(3) 通常の発達上のつまずきによってキレる子ども(このケースが一番多いようです。)
小学校へ上がるということは子どもにとっては未知なる社会へ放り出されることです。ものすごく大きなストレスがかかっている状態です。当然、学校への行き渋りやおねしょ、指しゃぶりなどの赤ちゃん返り(退行症状)が起きても不思議ではありません。
学校側も、他の子どもと同じようにできていないことを指摘します。この年齢の子どもにとっては同じようにできないのは普通なのに、それを要求するのが学校というところです。そして、親は、みんなと同じでないことや、普通ではないことに過剰反応をして、子どもを叱責します。それが毎日続くことで子どもは、当然、情緒不安定になってきます。学校でおちつきがなくなってきます。親も学校も子どもも、この悪循環から抜け出すことが困難になってきます。
このような子どもの場合、多動傾向は少しは認められるかもしれませんが、それは発達障害ということではなく、成長過程の中で適応化していくレベルのものであるという視点が大切です。最近は、教育現場でも発達障害を勉強される先生が増えて知識は身についているかもしれませんが、それが悪影響を及ぼし、発達障害でもないのにそのレッテルを貼ってしまい周囲もそのような目でみてしまうという弊害も現れています。
LD(学習障害)という状態は障害ではなく、教える側の創造性の足らなさを表現したものではないかとさえ思います。そのような子でも上手に教えれば理解できるのです。自分自身のことを申し上げると、私はADHD傾向ゆえ短期記憶が良くありません。特に聴覚記憶があやしい。ですから、WAIS(成人版ウェクスラー知能検査)の、数字やひらがなの読み上げを再生するテスト項目などは大の苦手ですが、指を使って視覚に変換することで、なんとかやり過ごすことができます。こういう工夫が学校の先生に必要であるということです。本を読んだり考えたりすることは聴覚で行っているので、学校の勉強などは聴覚記憶が弱い人にはキツイことが多い。けれどそれはマイノリティ(少数派)ではあるけれど発達の障害ではないですよ、ということです。
発達障害という診断は、精神疾患というよりも、そのような社会的な病理の側面もあわせもっているのです。マイノリティ(少数派)は淘汰されマジョリティ(多数派)だけが生き残る。これは大きくみる多数決を信条とする民主主義の弊害の一つと取れるかもしれません。発達障害と診断された子どもはたまりません。そのように診断(誤診)されて自殺した子どもも居るくらいです。私たちは、発達障害と言うときは、本当に気をつけて言うべきなのです。
通常の発達のつまずきによってキレている子どもは、過度の叱責という親や学校側の不適切な対応によって、子ども側で怒ったり逃げたりするという正常な反応が出ているということです。これは、不適切なのは親や学校側であって、子どもは適切であるということです。親や担任のほうが叱責することをやめて、子どもをまるごと受け入れて、おおらかに子どもの発達を尊重する姿勢をとることで、問題は消失します。
この場合、不用意に知能検査をしない、という姿勢は重要です。知能検査は心理検査の一部です。このような検査を受ける子どもたちの負担は想像を絶するものがあります。表面上は何食わぬ顔をしていても内心では「僕はこころがおかしいからこんな検査を受けているのだ」と自己否定感が当然働いていることに、気持ちを向けなければなりません。心理検査とは、とてもストレスフルなもので、受けること自体が自己否定へつながるのだという当たり前のことを忘れている教師や心理職が少なからず居るように思います。
面談で子どもが話す内容を注意深く聞いていれば、軽いADHD傾向などは、検査など実施しなくてもわかります。これらは、いわゆる個人差であって、それらを周囲が容認しながら大らかにかかわることで、問題は消失していきます。ここで、個人差を受け入れられないとすると(つまりマイノリティの否定)、それは教師や親のほうの問題である、ということになります。教師や親は、他人からの評価におびえ、先生としてよい先生、親としてよい親であると評価されることに揺れているのです。
□ 援助
(1)親や教師がキレる理由を理解する
キレることについて3つの原因をあげましたが、その記事の中にキレる理由も書いています。ここでは、どういう子がキレるのかという視点でまとめてみます。これらを正しく理解することによって、問題の悪化を防ぐことができます。これを心理教育といいます。子どもに教育するのでなく、親や教師にすることがポイントです。
キレる子のタイプとして2タイプあります。幼児タイプと前思春期タイプがあります。
幼児タイプは4歳~10歳くらいまでで、多動でおちつきがないために、授業に参加できず、自分を傷つけたり、友達に乱暴したり、暴言を吐いたり、虫や小動物を殺したりします。頭が怒りに支配されているために大人に反抗的な態度をとりますが、時々、べったりと乳児のように甘えてくることもあります。情緒が不安定で育てるのに苦労する子どもです。
前思春期タイプは思春期へ入る頃、すなわち小学校高学年から中学生になる頃、11歳~13歳くらいまでで、友達とのトラブルや叱られる場面などで不安になり、突然キレる子どもです。頭が怒りに支配されているために大人に反抗的な態度をとり、自分を傷つけたり、友達に乱暴したり、暴言を吐いたりします。それをとがめられると逆上して、いじめ行為がエスカレートします。
この両者のタイプにおいて共通していることは、これらの子どもは「安心感」「安全感」を感じることができない環境に置き去りにされているということです。
親に育児不安があり、その結果、虐待のような関係になっている。夫婦間の争いが絶えない家庭で育っている。親が病気(精神疾患を含む)で子どもを育てるゆとりがない。親が子どもに理想をおしつけて育てているため、ありのままの子どもを受け入れることができない。幼少期に重い病気にかかっている。これまでクラスで人気ものだったが急に注目されなくなって自分が悪いことをしたような感覚になってしまう。
これらはすべて子どもの安心感を奪うものです。これらが子どもにとってトラウマ(心的外傷)になって、不安な世界で生きている感覚に子どもが陥ってしまうと、じっとしていることができず、多動になりそれが暴力などの衝動につながっていきます。キレるという根っこには強い「不安」があるのです。ADHDの多動もチックも夜尿も同じです。この世は安全であるという感覚から遠いところで生きている、それがキレる子どもたちです。
(2)子どものトラウマ(心的外傷)を理解する
心に傷を負うと、まず身体に影響が出ます。なかなか寝つけなかったり食欲が落ちたり増えたりします。不安・怒り・憎しみ・恐怖・悲しみなどは心の底のほうで爆発しているために、表面的には、にこにこして元気、やる気まんまんで素直に見えます。
子どもは自分たちの周りの環境に自分を合わせます。そうしないと生きのびることができないからです。かつてオウム真理教の事件があったとき、信者の子どもたちが児童相談所に預けられました。そのとき相談所の職員がインタビューに答えて「彼らはとても自由で楽しそうに生活しています。」と言っていました。職員は、ここは前の場所と違って安全な場所なんだよ、ということを強調したかったのだと思いますが、子どもたちはそうは思ってはいないのです。「私は、ここでは楽しく生活したそぶりを見せないと生きていけないのです」と自分の心に命じて生活しているだけなのです。本当は親と生活したいのに、それでは日本で生きのびることができないので、自分の心に本心と違うことを命じているだけなのです。
そうやって「合わせて生きる」のが子どもなので、トラウマの多い環境の中に置かれると、自分の気持ちがズタズタになっていきます。不安・怒り・憎しみ・恐怖・悲しみなどが心の底にまん延していきます。しかしそれを大人に見せては生きのびることができないので、にこにこして元気な顔を表面的に作ります。この心の底の気持ちと表面的な顔の間には、高くて強固な壁が作られます。心の底の怒りや悲しみは嵐のように大きくなっているのですが、そのようなものを大人に見せてはいけないと思っているので、その壁はとても高くてちょっとやそっとでは壊れないものになっています。
このような心の構造が、解離と呼ばれる状態です。
そして、心の底に隠している不安・怒り・憎しみ・恐怖・悲しみは、身体的な症状として表現されます。下痢、吐き気、頭痛、アトピーはもとよりあらゆる身体疾患として表現されます。子どもはその苦しみを大人へ言うわけにはいかないので(言ってしまうと見捨てられると思っているので)、表面的ににこにこして従順な態度を装うのです。
先に説明した幼児タイプの子どもは、この壁のあちら(不安・怒り・憎しみ・恐怖・悲しみの世界)とこちら(ににこにこして従順な世界)を行ったり来たりしているのです。学校では怒りが爆発してめちゃくちゃをやっているけれど、家ではよい子をやっている。怖い先生には従順だが、やさしい先生には暴君になる。ある場面ではほとんど赤ちゃんのようにダダをこねるが、ある場面では大人のように物わかりがよい。このような別人格のような2面性を見せることが特徴です。
自分の中にはさまざまな自己の人格が居ます。一人の中にいい人の面もあれば悪人の面もある、それが人間です。自分という中に、複数の自己を保有して生きているのが人間です。ですから、幼児タイプの2面性も人間の特質の1つである、と言えるわけですが、その2つの部分が完全に分離されてしまっているところが解離の病理でもあるのです。普段、われわれが生活しているときは、さまざまな自分と折り合いをつけながら生きています。「ここは納得できないが今日のところは折れておこうか」とかやっているわけです。これは本質である怒りの部分と表面的な人間関係の部分、この2つを橋渡しできている状態です。
このように衝動と認知の部分がうまく手をつなげられるようにすることが援助の目標なのです。衝動は生命エネルギーなので無くす必要ありません。むしろそれを認知的なサポートによって上手に使えるようになることです。原子力エネルギーと制御棒との関係に似ています。また、この2面性の手をつなぐには2つの間の壁の高さが低くなっていることも必要です。富士山を越えていくよりは裏山を越えるほうが楽ですから。これらは、トラウマ治療の基本路線です。
前思春期タイプの子どもは、心の傷を刺激するような事態に遭遇すると、フラッシュバックが起きて、この壁を一瞬にして飛び越えることでキレてしまいます。顔つきも急に変わります。まるで別の人格が現れたような感じになります。このとき一瞬に解離しているため、自分で何をしているのか覚えていません。記憶がない状態で、盗みや仕返しなどの問題行動を起こすこともあります。
フラッシュバックとは、過去の記憶(あるいはニセの記憶)が一瞬にして目の前によみがえることを言います。通常、記憶とは、認知・情動・身体感覚・音・味・匂い・イメージなどの情報がひとつのまとまりとして脳の中で処理されて記憶されます。ところが耐えがたい記憶は、情動や身体感覚が切り離された状態で記憶されます。気持ちがそこに伴っていないわけなので、耐えがたい記憶もつらさを感じません。これは解離という心のメカニズムであり、それによって自分を守っていると言えます。つらい気持ちを感じてしまうと、生きのびることができなくなってしまうからです。
しかし、耐えがたい記憶を呼び覚ます刺激(例えば、音や匂いやイメージ)が外側から加わることで、切り離していた情動や身体感覚が、予期せずに一瞬にしてよみがえることがあります。これまで「ないもの」としていた感情が一気に押し寄せてくるわけなので、パニック状態になります。これをフラッシュバックといいます。このとき、意識は、その記憶が生起した場面に立ち戻っているわけなので、今という時間から切れているのです。キレる、というのは、衝動と認知が切れるだけではなく、今と過去という時間の連続性も切れるのです。
普通の子がキレるという表現をする場合、大人側のほうで、子どもの表面的な部分しか見れていないということが問題なのです。子どものほうでなんとか生きのびるために、大人が望む子どもであろうとしているために、自分で処理できていない未分化な怒りや悲しみや苦しみが混沌としたエネルギーとなって、感情が暴走するのです。
(3)多動とADHDを理解する
幼児タイプの子どもには、ADHD(注意欠陥多動性障害)という傾向を持つ子と、そうでない子がいます。ADHDでないのにどうして多動なのかというと、安心感や安全感が不足しているから大きな不安を抱えており、そのために多動になっているのです。
一方、ADHDの子どもは、外からの刺激に注意集中する能力が弱いために、じっとしていることができなくて多動になる、と一般的には言われています。
このADHDの多動は10歳頃を境に影を潜めて多動よりも不注意が優勢になってくるようです。成人のADHDの方は、多動よりも不注意問題が大きいと言えるでしょう。ただ、これはモノは考えようで、もともと多動のエネルギーは豊富にあるので、普通の子どもよりも数年遅いけれど、「集中」できる準備がようやく整ってきたわけで、これを利用しない手はありません。豊富なエネルギーと集中能力によって過集中状態になり、勉強やスポーツで大きく飛躍することも珍しくありません。ただ過集中というのは、身体的、心理的にオーバーヒートを起こしている状態です。前頭葉が真っ赤に発火して、ずっと続けていると心身が疲弊してきます。成人のADHDの方は、これに気がつかず業績を上げることに熱心になってしまう人も多いので、それについては十分に注意している必要があります。
ADHDの子どもには投薬によっても多動をクールダウンさせることができます。しかし、これは頭をマヒさせているのです。家庭や学校で、普通の子と反応が違うことで問題児扱いしていることが改善されていない場合、投薬は何の効き目ももたらさないかもしれません。投薬は環境調整と同時に行なわなければならないということです。他の子どもと比べて叱責することを止めなければ投薬は何の効果ももたらしません。
また投薬によって学業なども上昇しますが、それによって、頭のマヒ感とともに性格が変わってしまったという違和感を子どものほうで持つこともあります。この場合は、子どもとよく話し合って、子どもの意思を尊重し、投薬を止めるという選択肢も考えておくべきです。それによって、多動がぶり返すことになりますが、子どもが自分らしさを取り戻したということでもあります。この過程は、再発のように思いがちですがそうではありません。子どもは自分で多動を選ぶことで、大きく成長しており自尊心を持つことができるのです。これはその子の今後の人生において大きな推進力を得たということです。親御さんは、多動を選んだわが子を自慢に思ってください。
私見になりますが、ADHDの子どもへの投薬は意味がないばかりか、脳を痛めつけることになるので、子どもの成長にとっては避けるべき処方であると思います。
(4)感情のコントロールについて
人の心の中には、ネガティブな部分もポジティブな部分も両方あります。どっちかしかない、という人は居ません。その両方あることが自分で分かっていると、否定的なことに過剰に反応することもなくなります。
(2)子どものトラウマの理解のところで説明したように、心は、あちら(不安・怒り・憎しみ・恐怖・悲しみの世界)とこちら(ににこにこして従順な世界)があって、それらが壁によって区切られています。この壁が低いと、あちらとこちらが同時に見渡すことができるようになり、ああ自分の世界は不安だけではないのだな、ということがわかるようになります。
これによってあちらの衝動がこちらの認知と手を結ぶことができるようになり、衝動の暴走を抑えることができます。
これには大人の方が、「お前の不安・怒り・憎しみ・恐怖・悲しみ(あちらの世界)は在ってもいいんだよ」と承認して、支えてあげることが重要になってきます。支えるとは、その不安などを消してあげるのではなく、大人も自分の心の中で子どもの不安を感じて、自分もそこに沈んでみるということを意味します。それによって子どもがどれほど心細い状態に置かれているのか、どれほど甘えたいのかが身をもって体験することができます。これはとても難しい技術ですが、子どもが「大人に相談して自分は助かっているんだ」という実感を持てるのは、これ以外にはありません。
この大人からの支えを子どもが実感することによって、ネガティブな部分は在ってもいいんだと自分に承認を与えることができ、自分の居場所を確保することができます。安全感が出てきます。それによってあちらとこちらの壁も低くなり、感情が暴走することも少なくなっていきます。
21世紀に入って、ポジティブ思考がとかく推奨されがちですが、そういう流行に惑わされることなく、子どもには存在感をもって接して、しっかりと支えることです。ポジティブ思考を言うだけでは、子どもの側に、自分が支えられている感じがまったく沸いてきません。
(5)キレる子への援助の方法
次の順番でキレる子にはサポートしていきます。
○安心感を与える
まず安心感、安全感を与えることです。子どもが親や教師を「安全な人である」と思えるような行動をします。子どもはこれまで安全な環境の中で自分を発達させることができずに生きてきました。ある意味、ハンデのある生活をしていたわけです。ここで親や教師から安全な場を提供されることで、「自分は自分で居ていいのだ」という安心感が増大し、自分を行き直すことができるようになります。
○身体感覚を発達させる
不安・怒り・憎しみ・恐怖・悲しみ(あちらの世界)などの情動は、感情として記憶されているわけでなく、身体感覚として記憶されています。具体的には、喘息、腹痛、頭痛、下痢、アトピーなどの身体症状がそれにあたります。
これらの症状は、それらが出てくる前に身体の感じとして感じることができます。例えば、胸が詰まってくる、お腹が張る、肩が重くなる、肌が敏感になる、顔がこわばる、などです。これをフェルトセンスといいますが、それに意識を向けることで身体感覚の背後に隠された感情を発見することができます。発見したらそこに居るように促(うなが)します。この場合、サポートする人も一緒にそこに居ることが重要になってきます。相手を一人ぼっちにしないということです。これにはある程度練習が必要ですので、マインドフルなセラピーをご自分で受けることで、サポーターになることも可能です。
やさしく背中をさすってあげたり、ゆっくりと背中をたたいたり、一緒に深い深呼吸をしたりすることは、とても良い援助になります。このとき「ゆっくり」ということがポイントになります。相手の怒りや不安や憎しみを感じるとこちら側は防衛的になり、自分を見失って早い対応の仕方になりがちです。子どもをあやすというのは、「ゆっくり」ということです。誰も眠りに落ちていく赤ちゃんを急(せ)かしながらあやしたりしません。その感覚で身体接触を試みてください。
そして子どもの怒りがおさまって行ったら「怒りをおさめることできたね」と言葉をかけてあげます。こうすることで、身体が静かになる感覚と怒りがおさまるという言葉が子どもの中で一致します。身体と言葉(認知)がここで一致するのです。子どもにとって(大人にとっても)身体と認知が一致するというのは重要なことなのです。それはカウンセリングの視点から見て、言葉にならなかった自分の中で渦巻いていた感情が、言葉を得ることで自分の中で納得していく過程に他ならないからです。
○キレる瞬間を思い出させる
これはクライエントが自傷したときのカウンセリングと全く同じやり方です。キレる瞬間というのはだいたい解離しているので記憶にないことが多いです。ですから、まずやることとして怒りを納める体験をすること。まずは「納める」ことが基本です。トラウマワークの基本です。これはブレーキということです。いつでもブレーキをかけられるというコントロール感を身につけるということです。それには、子どもの持っているリソースを活用するのです。子どもが楽しいこと、ほっとするようなことをいつでも表現できるように習慣化しておくのです。これによって、キレる話をしている途中、解離しそうになったら、ブレーキをかける。つまりほっとする話を思い出させる、それを子どもに語らせるのです。こうすることで身体に緩みが戻ってきます。少しずつ前進するのです。そして、怒りを納めることができたら、どうして怒りが出てきたのかということを確認できる下準備が整ったわけなので、次は、キレたことを加害者の子どもと二人だけで面接します。被害者の子どもは同席させません。そしてキレる前のことを、事実関係をていねいに聞いていきます。
このとき加害者の子どもに子どもを評価したり判断をくだしたり、教育的・懲罰的にならずに、「そう言われたことはあなたにとってものすごく嫌だったんだね」と共感的に対応していきます。そしてキレる瞬間のことが話されたら、そのとき身体のどこか苦しくなったのか、嫌な感じになったのか、と質問します。この質問は、子どもの身体感覚=フェルトセンスを聞いているわけですが、この感覚は微妙な感覚なので焦ってはいけません。言葉にできないことも多いと思うので、そのときは絵を使ったりします。絵には感情がどこかに表れているからです。「そのときのことグルグル絵に描ける?」とやり方を変えたりすることもあります。
グルグル絵とは心理学用語に直すと、スクィッグルという絵です。めちゃくちゃに左周り、右回り、上下、左右に好きなクレヨンで線を描かせます。それを視線で追わせます。それによって隠されていた感情が表出してきます。
そして子どもが「胸がすごく押される」と表現したら、自分にすごく迫ってきた感じを受けたんだね、とても悲しかったんだね、居ても立ってもいられなかったんだね、とか、その感じを面接者が自分のフェルトセンスで感じながら、言葉で返していきます。このとき、面接者が自分のフェルトセンスとして子どもの胸が押される感じを感じていることが重要です。それなくして面接は進んでいきません。面接者がそのフェルトセンスを感じているからこそ、面接者から子どもに返す言葉が「真実の言葉」として子どもの心に届くのです。これを共感といいます。言葉というのはウソをつくものなので、言葉で対話するときはフェルトセンスを介在させることがポイントとなるのです。
こうやって自分の身体感覚に、面接者から真実の言葉をもらうことで、子どもの身体と認知が一致します。キレる瞬間、自分の中でいったい何が起こっているのかが、子ども自身にも納得がいくようになります。こうすることで感情が暴走するサイクルから離脱することができます。
○学校の環境を整備する
感情が暴走するサイクルから離脱することができるようになったら、それをキープできる環境が必要になってきます。
学校では、図書館や保健室や校長室へいつでも行っていい、という環境を保障することです。キレそうになったら、授業中でもいいので手をあげていいよ、ということを保障するのです。そして図書室で静かに本を読んだり、保健室や校長室でゆっくりと話を聞いてもらうことで、怒りをおさめる体験を繰り返すのです。キレそうになったら「教室を飛び出す」という行為によって、「自分で感情をコントロールできたね」とほめてあげるサイクルを作ってあげるということです。これがうまくいくと、この成功体験によって子どもの自尊心は増大します。そして自分に対して感じていた違和感というものが小さくなっていきます。
子どもは、できるなら暴力などはふるいたくはないのです。
○家庭の環境を整備する
キレる子どもがキレなくなっていくには、家庭が安全であるということが必要不可欠です。これなくして状況が改善することはあり得ません。ですから親への援助も必要不可欠なのです。虐待などがある場合、家庭内の暴力がひどい場合、保健所や児童相談所などの専門機関との連携も必要になってきます。
家族の問題を取り扱うことになるので、家族的アプローチ=システム論がわかっていることも重要です。両親のアルコールやDVなどの問題も多いので、児童相談所というより保健所との連携に比重が置かれるかもしれません。家族問題はソーシャルワーク的な発想が重要だからです。しかし現状としては、保健所でそのようなカウンセリングスキルをもった人も少ないので、「一緒にやりましょう」という姿勢を見せながら、保健士さんを(後ろのほうから)リードして、家族をカウンセリングへ登場させていくという戦略も必要でしょう。
このとき親は、「自分は親として失格である」というレッテルを貼られたと感じるだろう、ということは十分に理解しておかなければなりません。面接者は「そうではない」という態度をいつもキープしておく必要があります。親は、好きで虐待しているわけではない、ということをわかっていることです。生活環境や親が歩んできた道など、いろいろな要因があって子育てに余裕が持てなくなっている状態なんだな、と理解しながらサポートしていくことが重要です。
家族面接は、面接者のそのような理解のうえに立って進展していくものなのです。面接者がどのような視点をもっているかということがカウンセリングの成否に直接跳ね返ってくるのです。カウンセラーの力量が試される場面なのです。
親は、子どもにいつでもどこでも良い子でいてほしいと願うあまり、家でぐずぐずしていると、学校でもそうではないかと思い、つい家でちゃんとするように求めがちです。しかし、家でぐずぐずしているということは、家という場所は自分の感じたままを出してもいいのだという子どもの感情が行動化したものです。子どもの安心感の裏返しでもあります。家では子どもの感情を十分に引き出せるだけの機能が必要です。子どものぐずぐずは、家にはその機能がある証拠でもあります。こうやって家で自由に感情を出せるということは、学校という社会場面では、年齢に応じた社会性を学習できる能力があるということです。家で弱みを出せるということは、子どもの避難所としての機能が十分に働いているということで、ゆとりをもって子育てをしていく環境が整っているということです。そのことを親に理解してもらうことも面接者の役割の1つです。
□まとめ
親や教師がキレる理由を理解できるようになると、叱責することが逆効果であることがわかります。それがわかることで親や教師の子どもに対する態度が変化し、子どもは甘えられるようになります。子どもは甘えたいのです。なぜ甘えたいのかというと心細いからです。そういう不安があるのです。不安を親や教師に出せることができるようになると、キレることが減少していきます。これは子どもと親、子どもと教師の間の信頼関係を育てていきます。信頼関係ができてくると、子ども自身もキレる前に自分の状況を察知し、教室から避難して安全感を取り戻せる場所、例えば保健室とか校長室などへ避難することが自発的にできるようになります。そこで自分で深呼吸したり話を聞いてもらってマインドフルな自分を取り戻していきます。この行動の変化は、その子どもにとっての学校での評価を上げます。子どもは安心感を取り戻し、生徒や教師への対人関係の不安が減少していきます。これによって学級での適応がよくなっていきます。
キレる子どもたちは、自己評価の低さに自らが苦しんでいます。その自己評価を植えつけてきたのは親や教師、大人たちです。叱責や厳しい躾けによって、自己評価はますます低くなり、キレる悪循環を断つことはできません。キレる子どもに必要なものは安心感や安全感なのです。子どもの発達にとって、大人が安全な場所として存在していることが何にもまして大切なことなのです。右往左往しない揺るがない大人を見て子どもは安心して甘えることができるのです。
参考図書:
小学校における「きれる子」への理解と援助(大河原美以)
こころを聞く(崎尾英子)