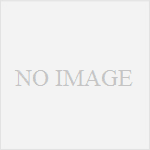吃音(どもり)とは言葉が滑らかに出ない症状をいいます。
DSM-5では、発達障害のコミュニケーション障害の吃音症という疾患名がついています。喉の発生器官が障害を受けているわけではなく、何かしら原因はわからないけれど言葉が発することができなくなった状態です。
精神医学的には、DSMと違って、吃音症は心因、つまり不安などの精神的ストレスによって引き起こされる病気という位置づけです。心理的な原因のある病気とされています。しかし、どもるのは、緊張するストレス場面ばかりではありません。緊張する場面ではスラスラと言えるのにリラックスしているときにどもったりもします。その意味では、神経症的な病とも言えません。なぜどもるか、これはとても興味深い問題なのです。
言語とはいったい何か、ものを伝えるとは何か、という哲学的な領域から考えるのも面白いかもしれませんが、それはしないでおきます。それをしたからといって、考える人の自己満足にはなるかもしれませんが、どもりの人が勇気をもらえることとは直接にはつながりませんから。
どうしてどもりになるのか、どうしてどもるのか、どもりは治るのか、これらについては明確な答えがないのが現状です。呼吸を変えたり、話し方をゆっくりしたり、考え方を変えたり、リラクゼーションをしたり、身体を緩めたり、発声練習をしたり、催眠暗示を与えたり、シャーマンに祈祷してもらってたりしても、それをやった一時(いっとき)は良くなることはあっても、また元へ戻るという不思議な障害です。
ベイトソンはすべての学習は回避的であると言っています。夜尿を例にとると、小学生になっても夜尿が治らないのは、夜尿が治ることで体験することが自分にとっては耐えられないことだから、夜尿を治すということを回避するのです。夜尿していると母親や父親から怒られるなど、気にしてもらえるという利得があります。両親から無視されているより怒られていたほうが自分にとって存在意義を感じたりできるために、親の気をひこうとして夜尿をするという学習をしてしまうのです。
これは情緒的な関わりが人間どおしの間には必要である、ということを示しています。ちょっと考えると、怒られる行動は修正されてもよさそうですが、人間というものはそういうふうには出来ていないんですね。いい子だねと肯定的な感情を向けられるときも、ダメな子だねと否定的な感情を向けられるときも、どちらも「情緒的」な関係です。その情緒的なものを求めるのが人間であるため、ほめられることか怒られることかの、どちらかを選ぶのです。つまり無関心以外のものを求めるのです。人間は無視されることを一番嫌うのです。
しかし、治療においては違うアプローチをとらないと治療になりません。この子にとって夜尿する自分は、親しみのある、なじみの自分です。夜尿しない自分は新しい自分です。
「おねしょしても、おねしょしないでいるのでも、どちらでも良いよ。おねしょしないということはあなたにとって新しい自分であり、それはとても怖いことかもしれない。けれど、おねしょしない自分を選んだら、新しい世界が見えてくるよ。新しいからね、怖いかもしれない。怖かったらね、怖いって言っていいんだよ。私と一緒にそれを見ていこうね。一人だと怖くても二人なら見れるかもしれない。そして、それが本当は怖いものでもなんでもないんだとあなたが心から思えるときまで、私はそばに居るよ。でもやっぱり、おねしょしようと思う自由もあるんだよ。あなたが安心するまでおねしょはしていいんだよ。そうやって私を何度も試してもいいんだよ。おねしょをしても、ちゃんとそばに居てくれるかどうか確認してもいいんだよ。おねしょすることで何かほっとしたこともあったけど、嫌なこともあったことは、自分でわかっているよね。こんな同じことを繰り返すことはもう止めたいという気持ちも自分の中にあることは知っておいてね。」
二人で見ようということは強制するのではありません。怖いと思っていた年月は膨大なものです。そう単純に怖さがなくなるわけはありません。焦ってはいけません。何十年も怖いと思っているものは簡単にはなくなりません。何ヶ月、何年かかるかわからないけれど、少しずつ小さくなっていけばいい。もう怖くなくなってそれが見れる時がやってくるまで、治療者は落ち着いてそこの場所に一緒に居ることです。無理やり首根っこを捕まえて見せるようなこととは根本的に違うことなのです。
このようなスタンスで居るのが治療者ですが、親もこのような立場に立つことで子どもにとっては福音となるのです。回避的となる学習をどうやって治療へ乗せていくか、親はどのようなスタンスでいるべきなのかを説明したわけですが、どもりも何かの学習だとすれば同じことが言えるかもしれません。
さて、どもりは何を回避しているのでしょうか。もし何かを回避していた場合、そこから逃げなくてもいいよ、と自分を許すことができれば、治っていくものでしょう。確かに思春期に一時的にどもりになるような子どもたちは、そのような神経症的なところがあります。その子たちにとっては、どもるということは症状の本質ではないので、本質の部分(回避している部分)が治癒することでどもりは自然と治ります。
しかし問題は幼少期からどもりの子たちです。この子たちが何を回避しているのか、その理由はいまだ分かっていません。もし回避しているとすれば、とても複雑なこころのシステムを使って、どもっているように思います。ここからは私論であり一般的な学説ではありません。個別的な当事者研究(私自身、幼少期からのどもりです)のことだと思って読んでください。
私が小学校の頃は、まだADHDという病名はありませんでしたが、今は、自分はADHDだったんだと思っています。落ち着きがなく、かんしゃくを起こし、授業中も教室を立って歩いていました。そのため父親からも行儀が悪すぎると注意され、時々ビンタをされていました。怖い父親ではありませんでしたが、そういう躾けをされていたわけです。小学校5年生くらいまでの記憶は断片的にほんのわずか思い出せるだけです。以前、子どもの頃を退行催眠でみてみましたが、これといった外傷記憶(トラウマ)もありませんでした。(催眠でなかったからトラウマはないとは言えないのですが、カウンセラーをやっていますので、そのくらいのことはしているという意味程度にとってください。)
記憶が整ってくるのは小6の頃からです。整ったというのは非常に正しい表現と思います。昨日の次は今日、今日の次は明日というふうに時系列的に記憶が連続してあるのです。トラウマを受けた人が記憶を蘇らせるのと似ているようですが、決定的に違うのは、私の場合は蘇ったわけではないということです。相変わらず小5までの記憶はぼんやりとしたままで、小6あたりからくっきりと記憶があるのです。そして、小6の頃から多動・衝動も収まっていったように思います。まさに10歳の壁を越えたあたりですね。
-ADHDは、脳の発達遅延で10歳くらいまでに通常の脳と同じ体積となる、またそのころに多動が収まっていって不注意が優勢になることが多い、という説に合致しています。-
私論では、このようなADHDの状態を回避するために「どもり」になったのかもしれないと思うのです。ADHDは落ち着きがないしキレやすい。それにストッパーをかけるために、どもりになったというシナリオです。どもりになると自尊感情は当然低下しますが、それが自分の内的衝動が暴走するのを止めるためのストッパーだったということです。もし自分が「ADHD+どもり」でなくて、ADHDだけだったとしたら、危険で過酷な思春期を生きていたかもしれません。周囲からも嫌われ自分でも嫌いになって最低の自尊心の中で絶望しながら生きていたかもしれません。もしそうだとしたら、これは本当に、人間のこころのシステムというものは手の混んだことをやってくれていると思います。
他の精神疾患で相談に来られる方に接していても同じように感じます。人間の精神というのは、まったくもって複雑なシステムで、精神の病気にでもならなければ、こんな複雑な自分に遭遇することもないのです。(余談ですが、自分はこんなに複雑だったのかと、自分のことを好奇心をもって眺められるようなると、疾患も治まっていくステージに入っていくようです。)
さて、回避という視点で眺めた場合も、この回避は良かったんだろうな、と思います。ADHDの子たちは、その二次障害として一般的に自尊心が低いのですが、それはあながち悪いことでもないと思うわけです。自尊心の低下が問題になってくるのは、周囲のものたちの影響で自分はダメなやつなんだと悲観するときです。周囲はなんとも思ってなくて、自分だけダメだと思っている分には、自尊心の低下もそんなに悪いものではないかもしれない、と思うのです。私の場合、周囲の環境が良かったのでしょう。それくらい環境というのは、精神疾患に影響を及ぼすということです。低い自尊心を持っていても、それがたいした影響をしないときもあるし、甚大な被害を及ぼすときもある、ということです。
どもりの研究をしたことがないので確定的には申し上げられないのですが、私自身を振り返ったとき、かなり複雑な精神の働きかけによって、どもっているように感じたりするわけです。
そのような複雑な精神が働く場であるためか、どもりというのは治りません。どもりの原因というのはなかなか姿を見せてくれません。世界の吃音研究の潮流としては、どもりを治そうと試みるわけですが、どもりってのはそう簡単には治りません。原因もわからないし、何から回避しているのかもよくわからない。自分の観察からは、横隔膜から上の上半身でどもっているようです。特に前頭葉でどもっているように感じますが、認知を変えるだけではどもりは治らないので、この前頭葉の感覚とはいったい何なのかは謎です。謎ですが、あ、どもるな、と予感したときは、頭の前と後ろの連結がうまくいっていないような身体感覚があります。(けれど、これは器質的なものではない、と断言できます。だから発達障害ではないのです。)
どもりというのは、このような不思議な症状なのです。ですから治そうと努力をするのでなく、どもりを上手に使ってください、それを生きる技術に使ってください、と言っています。自分のどもりを好奇心をもって眺めてみることです。
私は、思春期の頃は、人を前にして話す仕事につくとは思ってもみませんでした。カウンセラーとは人に何かを話す仕事だと思っていたわけです。しかし、それは違った。カウンセラーとは、人のこころを聞く仕事なんです。聞く仕事なので、話す必要はない。話す必要はないけれど、相談者のストレス対応能力をアセスメントしながら会話を水路づけしていく責任はあります。ここが聞きっぱなしとは違うところです。何かを伝えなければならないときは、一生懸命、どもりながら伝えます。これが良いみたいです。アナウンサーのように話すカウンセラーは重みがない、どこか嘘くさい、分かってもらっている感じがしない、ある相談者の方にそう言われました。こっちは一言いうときに、つっかえてどもるわけです。それが重厚に聞えるようです。取るに足らないことも何か意味あるように聞える(笑)、そういうメリットもあるわけです。
相談者を目の前にして話しているとき、自分がどもらずに流暢にしゃべっているなと感じるときがあります。そのときは、大抵どうでもいいことをしゃべっているので、しゃべることを慎みます。そして、ワザとどもってみます。どもることで、相談者を前にして自分が立つべき元の場所へ自分を戻すわけです。60分のカウンセリングでカウンセラーが話していいのは多くても10分程度です。
どもりの人は、胸にスッキリとしないモヤモヤしたつまり感と共にずっと生活しています。さらに、どもる直前、身体の中にさまざまな感覚が生まれます。この身体に感じる言葉になる前の感覚を心理学用語でフェルトセンスと言います。どもりとフェルトセンスとは切っても切れない関係なのです。私のカウンセリングのスタイルは、相談者と治療者(私)の双方のフェルトセンスにフォーカスしていくマインドフルなセラピーですので、自分がどもりであることがとても役に立っているのです。どもりであることで、自分のフェルトセンスの送信・受信機能がアップしていると思うのです。
最近、私はどもりを上手に使っているなと感じることがあります。どもりで悩むのは、それなりに辛いことですよね。しかし、どうか諦めずに、自分のどもりが生かせる場所を探してください。その場所はきっとあるはずです。自分の思いもよらないところに未来はころがっているはずです。飽くなき自分研究、どもる自分に好奇心を持ってこの研究を進めていってください。それができるのは、どもる貴方しかいないのです。