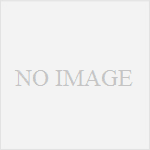カウンセリングが進んでいくと、様々な症状が納まっていきます。
そしてそのまま回復されていく方もいらっしゃいますが、それは例外と言っていいでしょう。実際、そのまま良くなられる相談者も多いのですが、それは例外であって、次の課題がやってくるほうが自然と考えたほうがよさそうです。
そのようにカウンセラー側では思ってはいるんですが、油断をしてしまうんですね。カウンセラーのほうも人間ですから、相談者の方が元気になっていくのを見て、つい嬉しくなって油断をしてしまう。
しかし、カウンセラーの役割は症状を納めることではありません。それで相談者の方が満足されるのでしたらいいのですが、本当のカウンセラーの役目は、症状を納めながら、次にやってくるだろう課題を見据えて、自分を内省していくこと。つまり、カウンセラー自身が自分の内面へ踏み込みながら、クライエントさんが問い掛けてくるだろう次なる問題の下準備をしていくこと、この体制がカウンセラーには必要なのです。クライエントさんの内面の問題を話し合っていながら、カウンセラーが自分自身の内面へも降りていくのです。
なぜなら、次にクライエントさんから問われる問題こそ、カウンセラー自身の存在が問われる難しい問題だからです。
次なる問題とは、「人はなぜ生きていかなければならないのか」という、答えのない問いなのです。
なぜ生きるのか、なぜ死ぬのか、なぜ苦しむのか、なぜ愛するのか、これらの問いは究極の問いです。答えはありません。
実際、このようにはクライエントさんは問いかけはしません。だから、カウンセラーのほうでぼんやりと聴いていると、この究極の問いが問われていることに気がつかない場合もあるでしょう。しかし、カウンセラーのほうが耳を澄ませて、クライエントさんからの問いかけを眺めていると、うっすらと問いの輪郭が見えてくるわけです。
これらの質問に、宗教、哲学、スピリチュアルからの視点を借りてきて回答することは比較的容易にできます。なぜならカウンセラーはその手の話に日ごろから親しんでいるからです。気の効いた返事もできるでしょう。しかしそれは、答えにはなっていないのです。なぜなら借り物の答えだから。それをすると、クライエントさんは確実に失望し絶望します。カウンセリングに来なくなります。
なぜでしょうか。
それはこれらの問いには答えがないことを、クライエントさんのほうでも、うすうす知っているからです。カウンセラーが答えられないことを知っているが、自分ではにっちもさっちも行けないので、止むに止まれずカウンセラーに問いかけるわけです。
「ねえ、先生。わたしはこんなことを考えてしまうのです。」
そのときカウンセラーは自分自身に深く沈むことを、クライエントさんから突きつけられているのです。お前は自分の人生をかけて、この問いを一緒に考えてくれるのか、そういう止むに止まれぬクライエントさんの苦悩があるのです。だから、カウンセラーも、自分の人生をかけて、その問いを一緒に見ていく覚悟がいるわけです。
このような根源的な、答えがない問いに対して、いとも簡単に返答する人物など信用できるわけがありません。クライエントさんはとても感受性が豊かです。単なる知識からの返事は簡単に見抜いてしまいます。底の浅い小手先のカウンセラーなど、すぐに見抜かれてしまうのです。
さて、
「なぜ生きていかなければならないのか」
この問いの背後には、自殺したいという行動が潜んでいます。カウンセラーもそのことはよく分かっています。だからこそ、腰を引くことなく、その問いに自分の総力を賭けるのです。総力をかけて自殺を阻止しようとするのです。
自殺する人のパターンを分けることなどできないと思うのですが、それでもあえてそれをやってみると、私の中では3つくらいに分類できます。(これは、私の少ない経験上の話として聞いてください。)
1.死にたいという強い衝動に動かされ、自殺する人。
2.普通に生活しているようだが、あるとき突然自殺してしまう人。
3.すべての問題が解決し(あるいは人生の意味が分かり)、もう生きている必要がなくなり、自殺する人。
1の人は、自殺衝動が身体全体にほとばしっているために、接しただけでもその苦悩が伝わってきますが、2の人の自殺についてはわかりづらいです。わかりづらいですが、1の人が回復されてきて、普通に生活を送れるようになってから、突然命を落とすことがある場合など、この2のパターンの人に似ているかもしれません。これは、うつ病の回復期に多くみられる自殺動機と似ているかもしれません。
死にたいという気持ちは、自分の中にすでに死んでしまったものがあることを示しています。これまで頼ってきた考えや感情が役に立たなくなった状態です。死にたいと思うことは身体的にはまだ生きていますが、精神的には何かが死んでいる状態です。つまり、何かが死んでいるため、その何かに変わるものが生まれ出ようとしている状態です。しかし、それは自分ではこれまで経験したことのなかったものだから落ち込むのです。そういう衝動が、1のパターンの人の内部には渦巻いています。
2のパターンの人は、意識に出てこない部分での苦悩を、内面の深い部分に持ちつづけている人です。「いないことにされてきた自分」を深い部分で持ちつづけている人です。
最近は「切れる」人の事件が多いように思いますが、この「切れる」ということも2のパターンに入ってくるかもしれません。切れるとは、「自分とのつながりが切れる」状態です。怒りが起こると、本当の自分がこころの中から立ち去ります。そのために自分の感情がコントロール不能になります。弱くてもいいのに、悲しんでもいいのに、そんな自分に納得がいかず、本来の自分を立ち去らせて自分を痛めつける行為が、他人への暴力という形で表出しているのです。
切れるとは、実は、自分へ怒っているわけです。怒りの矛先が自分へ向いている。つまり恨みです。怒りは相手へ感情が向きますが、恨みは感情が内向し自分へ向いてしまいます。恨みとは、怒りがレベルアップしたものです。
2のパターンの人は、外見は普通に生活しているようでも、こころの中は、自分とのつながりが切れやすい傾向にあるため、なぜ自殺するのかが自分でもなかなか見えにくいところがあります。しかし、実際は、こころの底に深い大きな悲しみがあって、それを自分で抱くことができない不全感に苦しんでいるのです。その不全感が、なかなか意識の上に昇ってこないため、周囲から見ると自殺するように見えないだけなのです。
話は少しズレますが、怒りのコントロールとは、怒りを抑えることではありません。怒りは生理的なものなので、それを抑えることは自分に対して大きなストレスとなります。私たちにできることは、その怒りの表出する正しい道筋を付けることです。例えば、のべつまくなしにどこでも怒りを出している人は、社会的に不利になりますし、なにより本人が気持ち悪くなります。そういう人は、できるだけカウンセリングルームの中だけで表出できるように道筋を付けていくわけです。これが怒りのコントロールの意味です。
認知行動療法では、怒りのコントロールとして、ひたすら台所やトイレをピカピカになるまで雑巾がけさせたり、食器を割ったり、大声で叫んだり、100mダッシュをさせたりもしますが、それはこの「正しい道筋」をつける一手段として捉えることができます。(高間注:食器を割ったりするよりは、トイレ掃除を徹底的にやるという効果のほうが高いように思います。1時間かけて汗をびっしょりかきながらやるのです。)
カウンセラーはただ聴いているだけのように思われるかもしれませんが、その面接場面を構成していく責任があります。聴きながら、クライエントさんとの会話の方向を逐一、観察し判断し適切な方向へ水路づけしているのです。怒りをカウンセリングルームの中だけに閉じ込める作業も、それを見据えながらクライエントさんと共同でやっている作業なのです。
さて、3のパターンは奇妙に聞こえるでしょうか。このパターンは、カウンセリングの終結時にも起こりうるパターンです。これは自己洞察(気づき)の問題です。症状はクライエントさんの洞察が深まるにつれて納まっていくことは事実です。けれど、自己洞察とは諸刃の刃(もろはのやいば)で危険なことでもあるのです。自分で気づいて良かったね、とカウンセラーはこころの中で思うかもしれません。しかし、この油断が「洞察の危険性」を招きます。クライエントさんが自己洞察するということは、実は自分でかなり危険な橋を渡りつつあるのだ、という視点を、カウンセラーは持ち続ける必要があります。
自己洞察の危険性とは、自己洞察によって「生きている必要がなくなった」という橋を渡ることです。日本に来談者中心主義のロジャースを紹介した友田不二男は、彼のブライアンの真空論で、「成長は真空ないしはひとりの状態でおきる。人間は人間関係の中で変化するのではない。人間はひとりぽつんといる時に変化し成長をするのだ。」と書いています。
あるクライエントさんがぽつんとつぶやきました。
「自分がひとりなんだと分かることはとても居心地がいい。もうすっかり棚卸ししたので思い残すことはない。」
ひとりで生きるということは、そういうことなのかもしれません。私は、そのとき、このクライエントさんを前にして「しんみりとした、ともし火のようなあなた」と感じていました。何も返す言葉がありませんでしたが、私はそのとき無限の言葉をクライエントさんから受け取り、成すすべもなく、ただただひれ伏していたように思います。私はこの言葉を、神様の啓示のように畏怖(いふ)の感情を持って聞いていました。
こんなときカウンセラーは、専門的な知識を盾(たて)にして向き合うことは無意味です。なぜならこのクライエントさんの感想は究極の問いであり、答えなどあるはずもない問いだからです。この問いが発せられるとき、カウンセラーは、これまで生きてきた自分の人生が問われます。
このときの「死にたいな」という気持ちは、尊重されるべきであると思います。そして、尊敬しつつ、死へ誘われつつあるクライエントさんへ対して、カウンセラーは立ち尽くすばかりです。
『その究極の問いについては、私は何もなすすべがありません。しかし、そのとても貴重なあなたの思いがどこからやってくるのか、私は知りたい。だから、これで終わりにするのではなく、あなたにしばらくお付き合いしたい。あなたから人間の深さというものを学びたい。』
こういう気持ちと共に、そこに立ち尽くしています。
こういう立ち尽くしているカウンセラーの気持ちは、ダイレクトにクライエントさんの中心へ響いていくようです。それによって、クライエントさんは新たな自分の人生を見つけていかれます。だから、このような問いに腰を引くのではなく、カウンセラーが教えを乞うように共同で探求させていただきたいという姿勢が重要なのです。
この状態は、精神科医の熊倉の言うところの、「究極的問いとは、人間についての問いである。人間についての問いは、人間そのものが謎だから、解決不能である。面接者は、来談者と同じ人間として、人間に固有の謎を抱えて生きている。来談者は、そのような問いを抱えて、面接を受けに来る。」という位置に、カウンセラー自身がとどまるということです。カウンセラーが、安易に回答に逃げないということです。教科書的なものや過去の経験から何か意味のあることを探すのでなく、いまの自分の立ち居地をクライエントさんにさらけ出し、クライエントさんに審判(しんぱん)を仰ぐということです。
こういうことができるカウンセラーは、なかなか居ないと思います。しかし、それにできるだけ近づけるように努力し続けることが、カウンセラーには求められることだと思います。
自殺をしたいという気持ちには、それぞれとても深いものがある、ということを、カウンセラーは自身のこころの底に沈めていくのです。
参考図書:ブライアンの『真空』論(ロージァズ全集 9 カウンセリングの技術)面接法(熊倉伸宏、新興医学出版社)