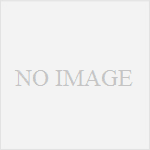幼児期後半はおよそ3歳~4歳までです。
3歳までは母子一体になって生活しており、母親との融合している合体感がありましたが、幼児期後半には、自分と他人との区別と、見捨てられ不安による怒りの表現方法を身につけることがテーマとなってきます。
まず「自他の区分」ですが、
3歳頃までは、幼児的合体感の中で生活しているので、自分と他人の区別はまだあいまいな状態です。このあいまいなものに境界を引いていくのがこの時期です。これは西欧的には自立ということですが、東洋的にみるとあまり適切な言葉が見当たりません。これは私のボキャブラリーの不足によるものですが、どうして、ここで自立という言葉が合わないのかというと、日本語の自立にはとても強烈なインパクトがあるからです。昨日までおっぱいを吸っていた赤ん坊に対して急に断乳するようなインパクトがあります。千尋(せんじん)の谷に突き落とされるライオンの子どものようなイメージがつきまといます。
自立というのは、幼児にとって、これまで一体感の中で依存していたものに対して「さあ、これからあなたは目覚めるんですよ」と不意打ちをくらわせることです。依存は英語でdependentで、自立はindependent です。dependentという言葉が残っている分、どことなくdependentを引きずっている気分であり、英語の自立のほうがまだ弱い感じです。日本語だと、依存と自立になりますので、自立という言葉の中には依存がきっぱり切り捨てられています。
しかし、independentというのは個人主義と訳されますが、ここには自己愛的雰囲気が漂います。私たちは、個人主義と利己主義は違うのだというふうに躾けられてきましたが、20世紀を生きてきた私たちには、それは同等のものだったという感慨があります。つまり英語の自立であるindependentにも、自己愛の雰囲気がオーバーラップしてくるのだということも覚えておくほうがよさそうです。「自他の区分」を表現する言葉として、自立は強すぎるしindependentは勝手すぎるわけです。日本もアメリカも「自他の区分」については苦労しているわけですね。
では、自立の代わりにどんな言葉が適切かと探すと、自己分化(differentiate)あたりが妥当ではないかと思います。自分と他人は違うのだ、という意識です。これはとても高度な意識状態であり、真の自己分化が達成されるのは成人期30歳以降ですが、すでに幼児期にその芽があるのです。正確に言うなら、もっと前の時期にさかのぼれます。
新生児期にも赤ちゃんは、母親とのやりとりの中で自分の調子を母親に合わせたり、母親に無頓着になったりしているのです。いつもいつも母親と同調しているわけではありません。自分からコミュニケーションを「外す」ことをやっているのです。同調する時間が1/3、同調を外している時間が1/3、同調へ向かって準備する時間が1/3くらいです。つまり生まれて落ちてから人間は、自己分化の道を歩み始めるのだということです。自己分化はDNAにあらかじめプログラムされているということです。これはちょっと感じてみると、寂しいものかもしれませんが、人間というのはそういう孤独に親和的な生物なんですね。この寂しさに圧倒されると依存症やパーソナリティの問題が出てくるのです。
ここで自己分化という用語の説明をしておきます。家族療法のボーエンが考えた概念です。自己分化とは、個人が日常生活の中で他の家族メンバーの感情や思考や不安に巻き込まれずに自分のポジションをもっているということです。いつまでも親の役や子の役を下りられなかったり、夫婦の問題に子供や実家の親などの第三者を巻き込んだり、中年になっても自分の実家が正しいという考えから抜けられないのは自己分化が育っていない状態なのです。実家からすっかり独立しているように見えても、心理的になんとなく実家に距離を置いてしまう、実家に帰ると理由はわからないが調子をくずしてしまう、こういう人もいらっしゃるかと思いますが、そういう人は自己分化の度合いが弱いとみます。
自己分化の度合いが高い人は、対人関係でストレスがかかったときも、落ち着いて自分で居られることができます。その場から立ち去りません。慰め役を他人に求めることなく、自分で自分をスージングする(沈静する)ことができるからです。これをマインドフルネスと言います。(鎮静は無理やり落ち着かせることですが、沈静は自然に落ち着くことです。この違いをしっかりと感じてみてください。マインドフルネスとは人為的なスキルではなく、自然の流れに沿ったスキルなのです。老子はマインドフルネスを無為自然と表現しています。)自己分化をについては、パートナーと親密さを作る上でなくてはならないもので、セックスを豊かなものにする根源となりうるものです。その話題とからめながら、成人期に詳しく見ていくことにします。
幼児期の話に戻りますが、他人が遊んでいるおもちゃを取り上げて自分のものにする、これは自他の区別がついていない状態であり、あのおもちゃは自分のでなく、○○ちゃんのだ、ということがわかっていることが自他の区別がついていることです。自他の区別がついてくると、人の顔色を読む知恵がついてきます。これと同時に人見知りも始まります。ここまできて初めて、自分は親に依存して生きているのだということがわかるようになって、幼児の万能感が幻想だったのだということに気づいていきます。
この幼児的万能感が消えていくことで、自分が親に嫌われて捨てられてしまったらどうなるのだろう、自分はちゃんと生きていけるのだろうかという不安感がでてきます。これが幼児期後半のもう1つのテーマである「見捨てられ不安」です。
見捨てられ不安とは、自分が依存している相手に嫌われて捨てられてしまうという不安です。ここは人間なら必ず通過する場所です。発達障害だろうがなんだろうが、ここは必ず通過していきます。依存症(嗜癖)の方は、ここがうまく通過できていないのです。見捨てられ不安が高いので、人と親密な関係になることが怖くなります。このような人が大きくなってパートナーを持つようになると、ゆがんだ親密さを形成してしまうことがあります。
先の話で自己分化の話をしましたが、マインドフルネスな状態でいつも自分の場所に立つことができる、何かあっても自分で自分のストレスを減らすことができる、このような状態になってはじめて、他人と親密な関係を持つことができます。離れているけど一緒に居る、という状態です。
これは幼児期前期の課題である、ひとりでいる能力ともつながってきます。ひとりでいる能力とは、ふたりいるからひとりで居られる能力、ということでした。見捨てられ不安とは、ひとりでいる能力の延長線上のものなのです。
ゆがんだ親密さとは、相手を遮断するか、しがみつくか、という関係です。アルコール依存を考えてみます。しらふのときは相手と距離をとって自分の独自性ばかりを主張します。しかしいったん酔いがまわると幼児的万能感に浸って、相手との垣根を飛び越えて相手と急速に一体化しようとします。これは恋愛依存も含んだ、あらゆる依存症の方の基本的な行動原理です。どうして、いつも一体化しないかというと、しらふのときは自分の見捨てられ不安を否認しているからです。こういう複雑なブレを持って生活を送るとなると、周囲も大変ですし、なにより、自分は何者かわからなくなり、空虚感に没入していってしまいます。
見捨てられ不安が出てくると怒りの抑制が起こります。これは、人生において友好な対人関係を築く上で非常に重要な学習となります。本来、見捨てられ不安とは良いことなのです。そういう不安があるから他人が嫌がることはしないようになるわけです。これは、他人の顔色をうかがって過剰に適応することですが、それだけではなく、自分自身が気持ちがいい状態を保持するには、自分自身が傷つかないですむには、どのようにしたらいいのか、ということにつながっていくわけです。マインドフルネスに自分を保持するための1つのきっかけになるわけです。ですから、見捨てられ不安というのは無駄なこと、体験しないほうがいいことではなく、自分の足で立つためには、必要不可欠なものなのです。
自分の怒りをどの程度主張するのか、怒りを相手が受け入れられるように表現を和らげる、自分が不安にならないような主張の仕方をする、そのような対人コミュニケーションを発達させるためには、見捨てられ不安は必要不可欠なものなのです。これらによって自己分化が発達していきます。相手を尊重しながら、自分も尊重するという在り方です。
これはアサーション(やわらかな自己主張)ということですが、アサーションと言ってしまうと対人スキルが前面に出てきてしまって大切なポイントを見逃すおそれがあります。大切なポイントとは、あくまでも自分の中に焦点が当たっていることです。相手へ焦点が当たってしまうので、こちらは不安になったり気持ちが満たされなかったりするわけです。あくまでも自分の中心部分へ沈みこみながら相手と交流する、というマインドフルネスな態度が重要なのです。
自分の中心に焦点を当てるということを、合気道の創始者である植芝盛平は、攻撃する相手に焦点を当てるなということで説明しているそうです。
相手の目を注視するな(催眠にかからないため)。相手の刀を見つめるな(恐怖を抱かないため)、相手の姿全体に視線を合わすな(相手に生気を奪われないため)。相手をこちらの世界へ連れ込むことである。そうすればこちらは居たい場所に立つことができる。
この合気道の注意分散の極意は、自分の怒りを有効に利用するための極意でもあるのです。相手との対人関係に困ったときは、まず相手のことを考えるのではなく、自分へ沈み込むことなのです。
実際には、足の裏、下肢の屈曲している側や耳の裏、首から肩にかけての穏やかなライン、ひじの内側などに関心を向けると良いです。こうすることで私たちを縛っている重力への気づきがおだかやに私たちを鎮めて、安定した自分の中心へ意識を向けることができます。自分の中心とは、自分の腹の底の位置にあります。こうやって自分で自分のことを愛撫できるようになると怒りが違う形で鎮まり、危険を与えてくる相手へもそれが伝わって、相手からの謝罪が引き出せるようです。謝罪を得ることで自分が抱いた怒りはしぼんできます。怒りは生理的なものですから持つことは良いのです。こうやって自分で怒りの収まり先をコントロールできることが重要なのです。同時に、そのような刺激によって自分が怒りを覚える(自分を見失う)ことに対しての気づきが生まれてきます。あ、私ってこんなことで怒るんだ、という気づきです。このように自分が見えてくることががもっと大切なポイントです。
怒りを抑制することは人生において重要であると申しましたが、この怒りが、脅しによって抑制される状態になると、本来の正常な発達からそれてしまい、怒りを押さえ込む役割を自分で選ぶようになります。このようになってくると病態としての(みなさんご存知の)見捨てられ不安にシフトしていきます。例えば、家庭内で暴力が横行していたり虐待があるような環境では、幼児は生きていくために怒りを抑圧します。自分の怒りを表面化させてしまうと、殴られたり食事を与えてもらえなかったり、生きていくのに必要な世話をしてもらえず、身が危険になるからです。
そのため、いつもニコニコしています。ニコニコ仮面です。おねだりしたいのに相手に要求しないのです。相手へ要求しなければ怒りを抱くこともないので、要求することをやめるようになり、ものすごく従順なよい子となります。それは親にとっては育てやすい子ですが、当人にとってはかなりの犠牲を背負っているのです。しだいに感情がマヒして恨みへつながっていきます。うらみはやがて自分の方へ向くようになり、その子のこれからの人生においての人間関係が狂い出します。
親に要求することをおそれて要求しなくなるということは、要求が満たされたときに嬉しいと思ったり感謝したりするという高度な感情を体験するチャンスを奪ってしまいます。そのため感情がマヒしていくのです。成人で、感情が不安定な人や希薄な人はこのへんに問題が固着しているのです。
怒りが抑圧されると、外面的にはおとなしくなりますが、こころの中に怒りが渦巻いている状態になります。この状態では怒りが自己主張につながることはなく、安全な形で表出させることができません。こころの中はとても圧力が高くなっているのに、それを出すことができないという、いわゆるトラウマの状態になります。怒りの感情を感じるなと自分に命令するので、感情が凍りついて平坦な表情になりますが、こころの中はものすごい怒りの嵐が吹き荒れているのです。エンジンでいうと、ブレーキを踏みながらアクセルを全開にさせている状態です。これが長く続くとこころが疲弊してしまって元にもどらなくなる、ということは分かっていただけると思います。この凍りついた怒りは適切な形で外へ出す必要があるのです。そうでないと、ずっとトラウマとして抱えたままになり、対人関係を極めて不安定なものにしてしまいます。
怒りが貯めこまれると、しだいにそれが恨みに変化していきます。体内に溜め込まれた怒りが発酵してガスが発生している状態、便秘状態を思い浮かべてください。怒りが変質したガス(恨み)は自分の体をむしばみます。怒りが恨みに変化してその鉾先(ほこさき)が自分へ向くのです。怒りとは「ほしい」という気持ちが受け入れられないことで生まれてきました。怒りが変質した恨みは「もっとほしい」状態になっています。恨みというのは怒りより強烈なのです。もっと欲しい、もっと欲しいと、愛する相手へ気持ちを向けます。けれど都合よく、その欲求を満たしてくれる人など存在しません。そのため愛情を欲求する相手が恨みの対象になってしまうのです。愛しているのに憎んでしまう、このような絶望的な状況に居るのが依存症の人たちです。感情がマヒして生きる喜びがもてなくなり、危険な人生を歩んでしまうのです。
大人の場合、溜め込んだ怒りが適切な形で自己主張できないと、関係ない人へ八つ当たりをしたりします。これが、自分で八つ当たりをしているのだということが分かってくると、その怒りも客観的に見れるようになってきます。そうすると、嫌なことがあったりしても、それを貯め込まずに誰か知人に愚痴る能力がついてきます。これが正しい怒りの処理方法なのです。
子どもの場合は、夜尿、チック、ぜんそくなどの身体症状として出てくる場合が多いです。親が子どもに対して、この子は手のかからない良い子であると思うのは、子どもに依存していることなのです。そのように子に期待するから、子どもは甘えたくても甘えられず、親に心配をかけまいとして、自分のこころに命じるのです。「私は親に迷惑をかけてはいけないのです」と。(これをベイトソンは相補的関係と呼びました。)この命令によって自分で自分のこころをしめつけることとなって、それが身体化するのです。小学校低学年で自家中毒のひどい子などは、幼児期後期の怒りが抑圧されているかもしれないのです。
参考図書:
カウンセリングに生かす発達理論(遠藤優子)
子どもを支えることば(崎尾英子)
愛という勇気(スティーブン・ギリガン)
パッショネイト・マリッジ(D・シュナーチ)